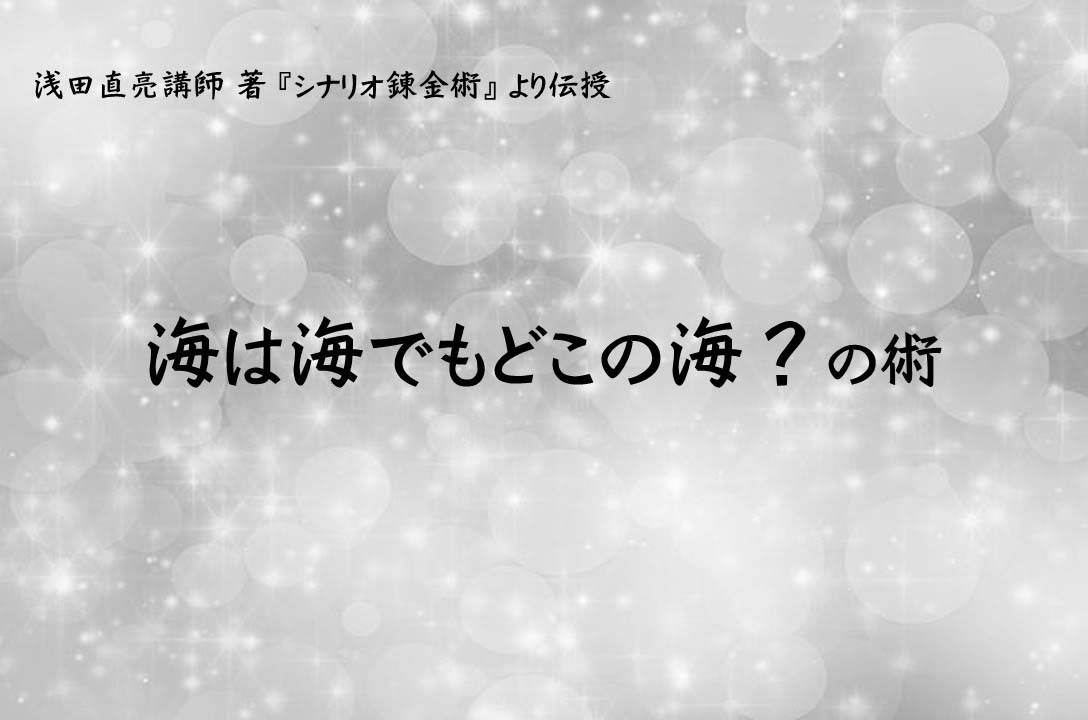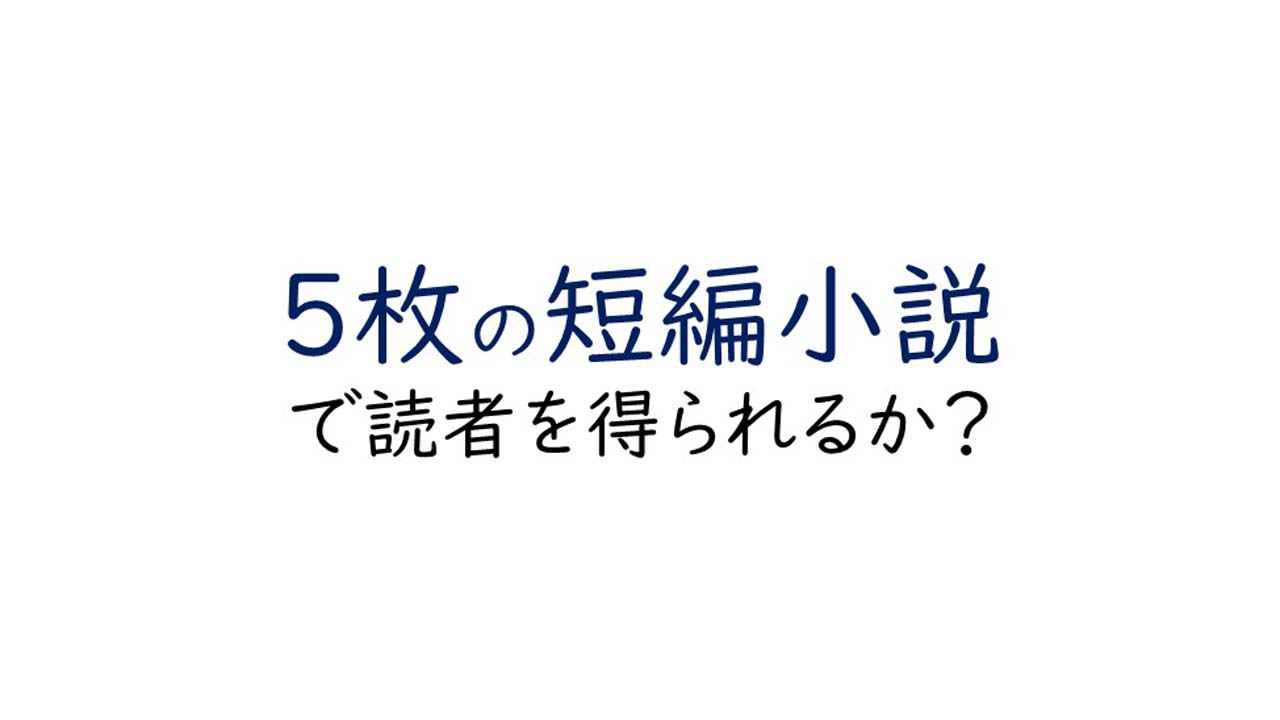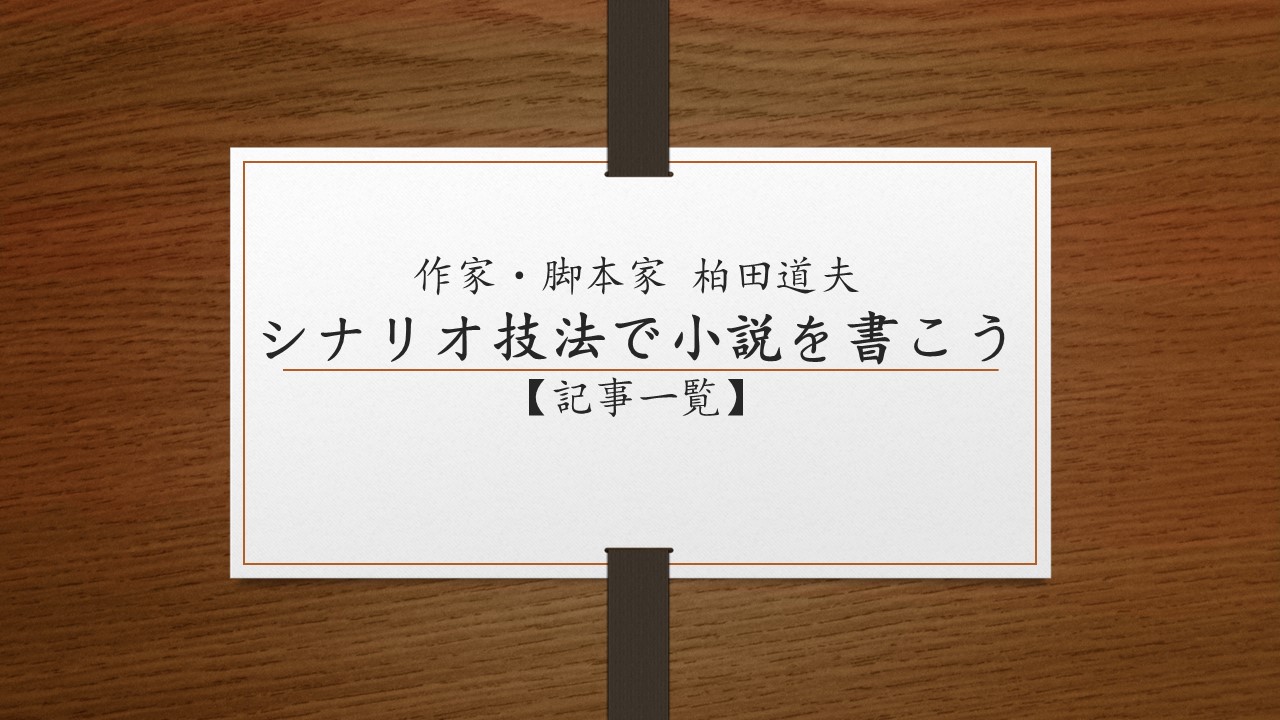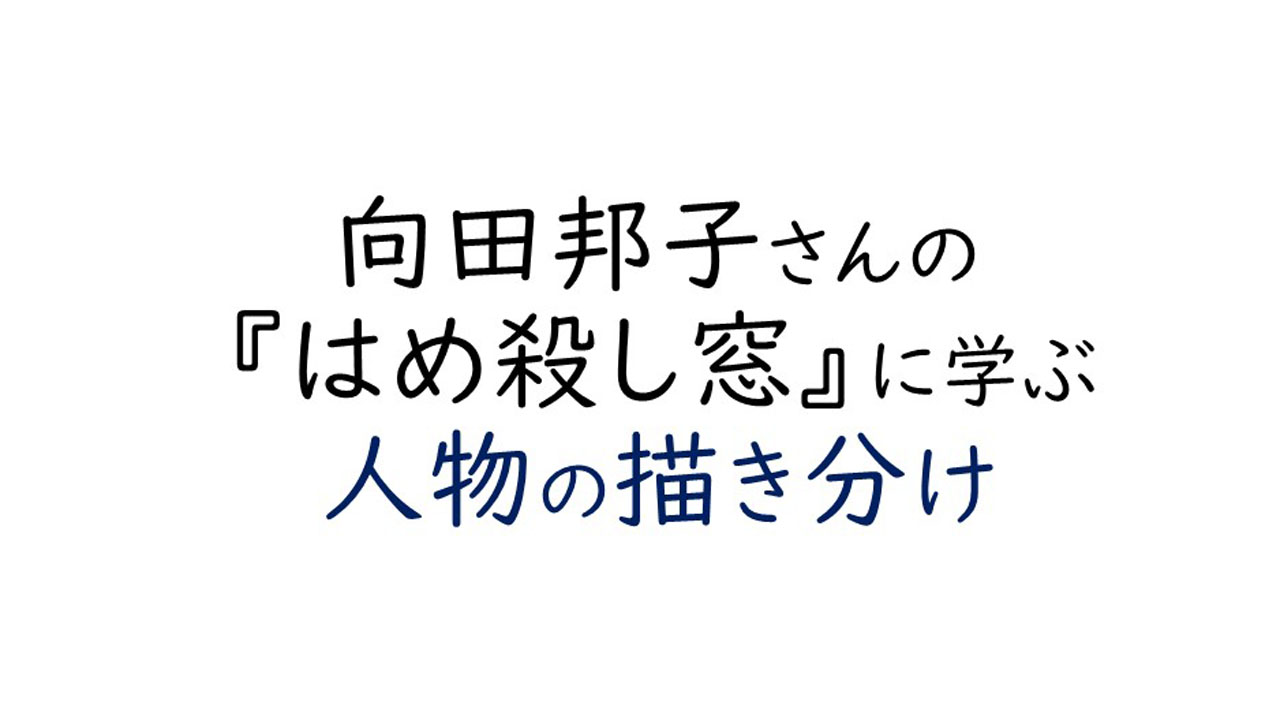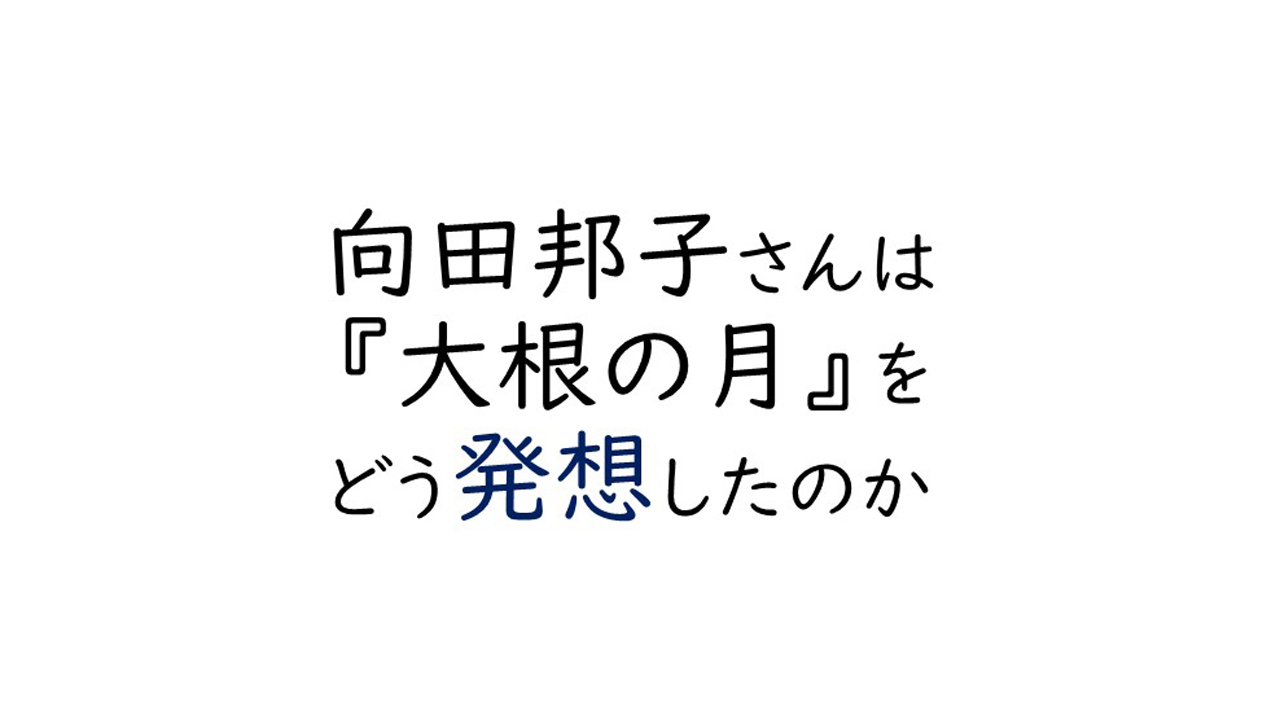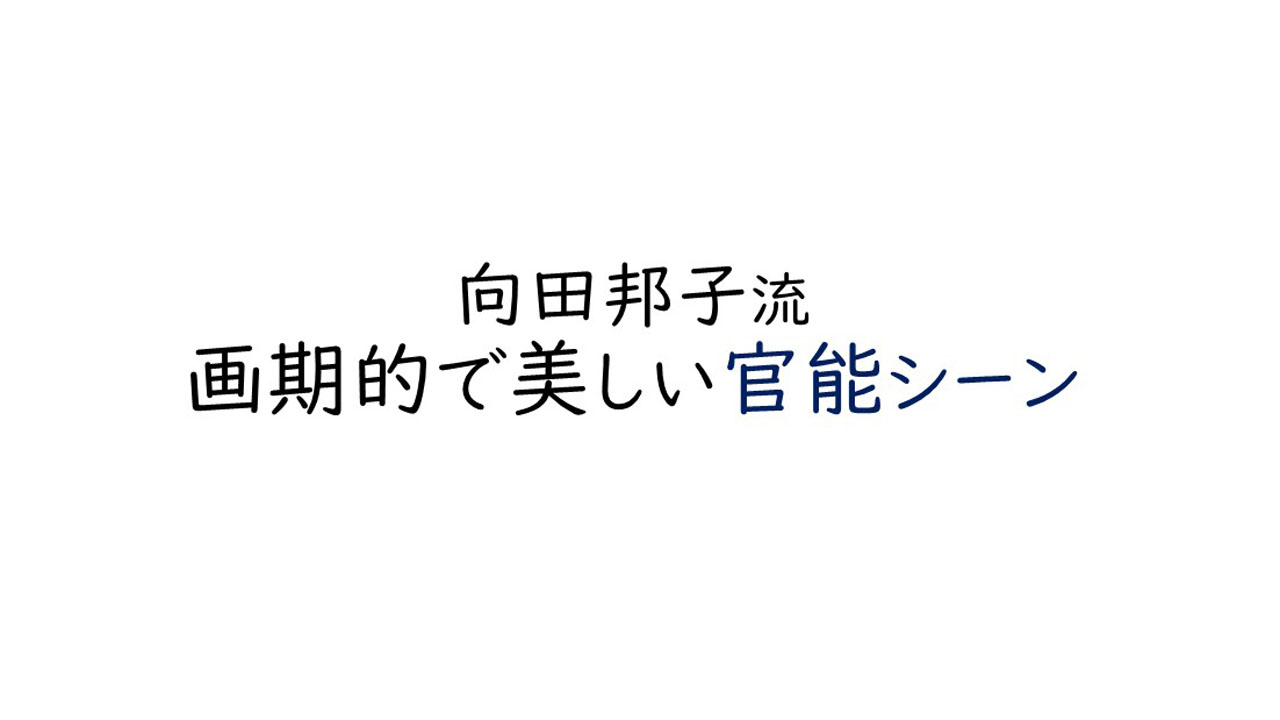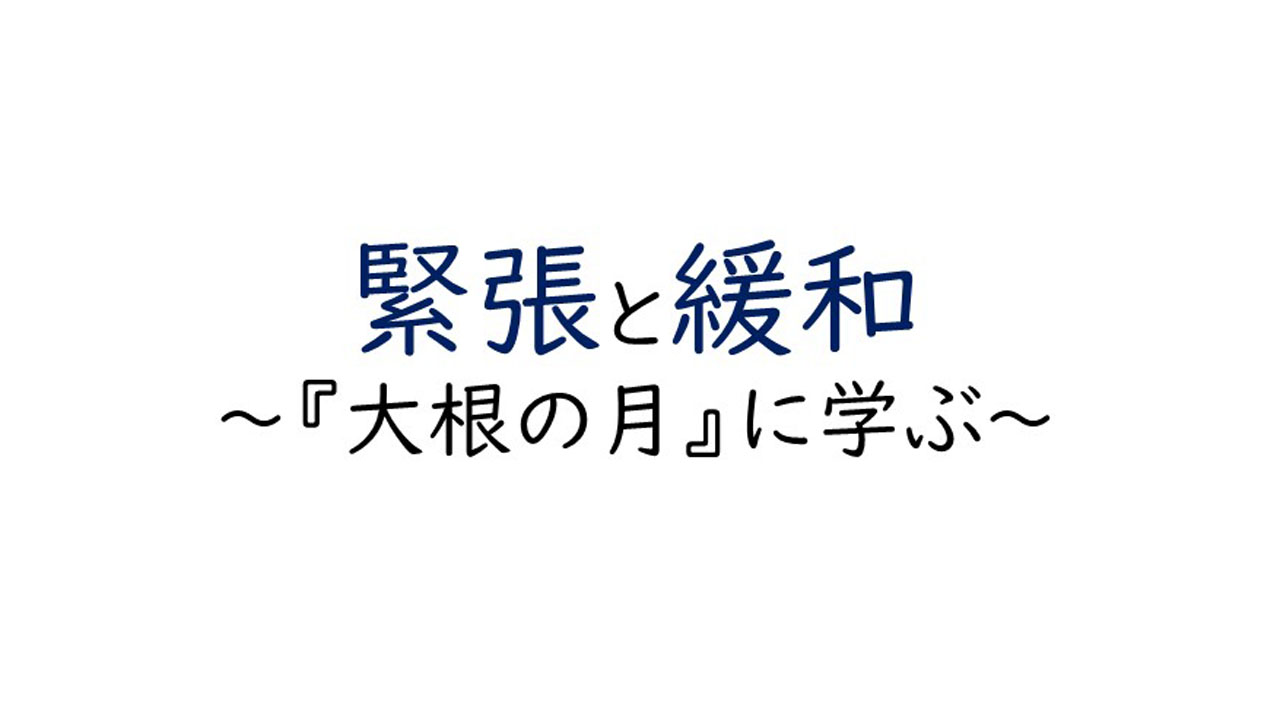活動弁士は日本独自の文化
――周防監督にとっては『舞妓はレディ』以後5年ぶりの作品となりますが、準備はいつ頃からしていたんですか?
〇周防さん:『舞妓はレディ』のあと、実は別の作品を準備していましたが、それを流して3年前から『カツベン!』の製作に入りました。
――脚本の片島さんがずっと温めていらした企画だそうですね。
〇片島さん:最初に興味を持ったのが20年くらい前です。
もともと無声映画が好きだったんですね。僕は熊本県出身で、昔は市内にもそれほど映画館がなくて、たまに父親に映画に連れて行かれると戦争映画で、姉に連れて行かれるとミュージカル映画ばかりで面白くなくて、映画少年というわけではありませんでした。
ところが中学1年くらいの時に、チャップリンの無声映画をリバイバルで観まして、面白かったのが興味を持ったきっかけです。
――チャップリンは、何を観たのですか?
〇片島さん:『モダンタイムズ』『街の灯』『キッド』の3本立てでした。
――あの頃の無声映画は、文字があってほぼ音楽が流れていて、弁士はいないんですよね。
〇片島さん:それが20年位前、たまたま観たテレビの情報番組で活動弁士を紹介していたんです。
日本では無声映画時代には活動弁士の語りがつきもので、当時は俳優さんや監督さんよりも花形で、大スターだったと。弁士が自分で台本を作るので、同じ映画でも弁士によって内容が変わるし、お客さんの目当ては贔屓の弁士で映画を観る事だったという話に興味を持ちました。
活動弁士って日本独自の文化なんですね。その時は知らなかったけども。その後、澤登翠さんという、関東で第一人者の方の活弁で無声映画を見て感銘を受けたんです。まるで3D映画を観ているかのように立体的に内容が入ってきて、いつか活動弁士の映画を作れたらいいなと思いました。
――澤登さんの舞台ではどんな映画を掛けていたんですか?
〇片島さん:おそらくグリフィスの『散り行く花』だったと思います。
――澤登さんにはお会いになったんですか?
〇片島さん:実際に澤登さんや片岡一郎さん、坂本頼光さんに取材し出したのは、周防監督が監督してくださるということが決まって、映画の企画が実際に動き出してからです。
それまでは図書館に通って、こつこつと調べていました。無声映画時代に実際に弁士をやっていた方は、もうほとんどいないわけですから、資料で調べて、あとは想像でホンを書きました。
第一稿を書いた後、関西で活動されている弁士の井上陽一さんに何度か取材しました。まだ、片岡さんや坂本さんの存在を知る前です。
そうやって直したものを、周防監督が『舞妓はレディ』の仕事を終えた頃に「こういうホン書いたんですけど、読んでもらえませんか?」とお見せしたわけです。
――ホンを読まれて、監督はどういう風に思いましたか?
〇周防さん:素直に面白いと思い、「これは絶対に映画にしたほうがいい」と話しました。でも自分で撮るつもりで読んだわけじゃないんです。
脚本を読んだ時は、監督というよりは、映画ファンとして面白いなと思いました。僕自身は、若い頃から活動弁士というのをまったく無視していたんです。
フィルムセンター(現・国立映画アーカイブ)に通って、ほぼ無音状態のサイレント映画も随分観ましたが、その中で小津安二郎の『生まれてはみたけれど』なんて観ちゃうと、「音、いらないじゃん」と。サイレント映画なんだから、サイレントで観るべきだと。活動弁士の存在は知っていたけど、余計なものだと思っていたんですね。
でも片島さんの脚本を読んで、あの時代、世界中で本当に無音の状態で観ていた人はいないよなと思ったんです。欧米でも音楽はずっとあったわけだし、エジソンが発明した『キネトスコープ』は箱を覗いて動画を観るんですけど、横にチューブが出ていて音楽が聞こえるという装置もある(チューブから音楽が聞こえたかどうかは不明)。
その後、リュミエール兄弟が『シネマトグラフ』を作ってスクリーンに投影して観る方式が主流になりましたが。初期の頃から映画監督は映画を撮る前提として、映画は無音で観られるものじゃないって知っていた。
それで活動弁士って何かということを改めて考えてみたくなった。片島さんの脚本は、第一に、みんなが忘れている活動弁士の存在を思い起こさせる点、第二に、活動弁士たちの物語を活動写真のように撮る、という点が面白いと思いました。
――活動弁士が、当時8000人もいたとは知らなかったです。日本だけ発達したのは、落語とか講談があったからなんでしょうか?
〇片島さん:そうですね。やはり古くから日本独自の話芸が存在していたことは大きかったと思います。人形浄瑠璃もありましたし。
〇周防さん:江戸時代から影絵を見せるものがあって、それにも語りが入っている。紙芝居にだって語りがあるわけですし、無声映画に限ったことじゃない。無言で動くものがあったから説明をつけたという自然発生的なことだと思います。
考えてみたら『キネトスコープ』にしろ『シネマトグラフ』にしろ、横に人が立っているわけです。映画がこの世の中に生まれたその日から、誰かが説明しているんです。