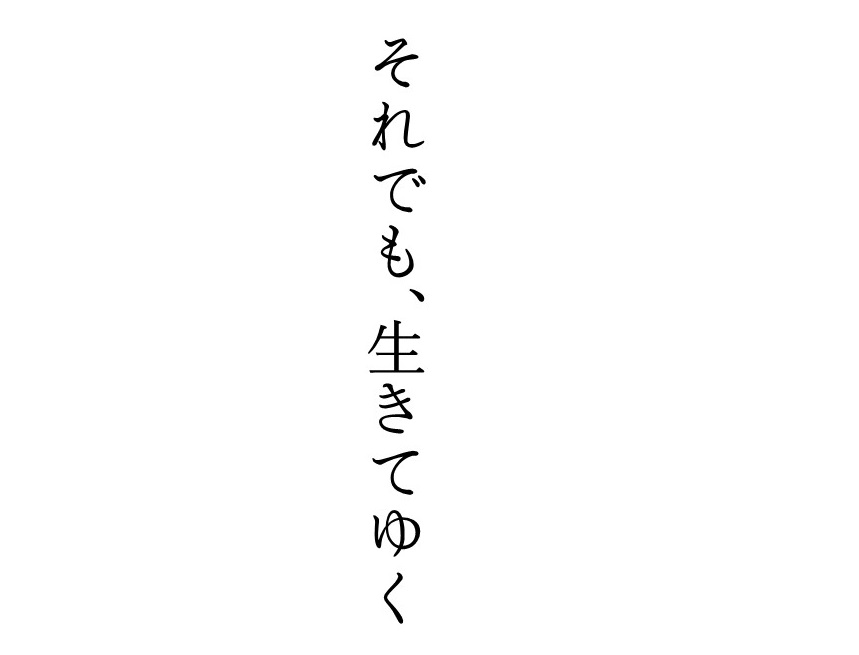ひとりの弁護士との出会い
『それでもボクはやってない』のシナリオを書いていた時に参加していた刑事弁護の勉強会で、ひとりの弁護士さんと出会いました。
その方が、今回の原作となった「命の終わりを決めるとき」(のちに「終の信託」と改題)の作者である朔立木さんです。
この小説を読んでいる途中から、僕は「これは映画らしいな」と感じました。
検察庁の前に佇む女がいる。
徐々に職業や名前がわかり、待合室に通されていつ始まるかわからない取調べを待つ……。
そういった描写から濃密な空気が伝わってきて、朔さんはこれを活字で表現しているけれど、僕は映像で見てみたいと。
一読しただけで、この小説が持っている映画的雰囲気とテーマ性、その両方に、僕は「これだ!」という感想を持ちました。
さらに読み進めると、主人公の折井綾乃という女医に、バレリーナ時代の草刈民代の姿が重なってきた。そうすると患者の江木という男は役所広司さんの顔になっちゃって(笑)。
すぐに草刈に本を渡して、「これを映画化しようと思うから、読んでみてくれ」と言ったほどです。こんな経験は初めてでした。
この小説は、このまま映画になるんじゃないかと思ったんですね。映画化するために構成を変えたり、どこかを端折ったり足したりする必要はないんじゃないかと直感的に思った。
そこで、このままシナリオにしてみようと、小説がハコ書だと自分に言い聞かせて、最初から最後までダイジェストにするような形で書いていったんです。そうしたら、「あ、いける、これは大丈夫だ」という感覚がありました。
この1稿目を書いた後、僕が一番気になった点は医療シーンです。
司法に関しては僕も十分取材をしていたし、作者自身が法律のプロですから、そこは心配なかった。そこで早速お医者さんに監修してもらい、おかしいところがないかどうか、事細かに確認をしてもらいました。
すると現代の医療ではおかしいとされる部分も見つかり、そこをどうするか、少し悩みました。
例えば綾乃が睡眠薬で自殺を図るというシーン。
今は、睡眠薬では自殺できないそうです。「医者が自殺しようとしたら、確実に死ねる方法がいくつもある。睡眠薬で死ねないのは医者にとって常識だから、小説の通りだと不倫相手の高井に対する嫌がらせにしかならない」と言われてしまった。そもそも自殺する意思があるかどうかが問題だった。
すると、取材していたお医者さんから「なら、お酒飲ませちゃえば?」とアイデアをもらいました(笑)。
医局には絶対にお酒が置いてあるそうですね。明確な意思を持たないまま自分の気持ちを紛らわせるためにお酒と薬を飲み、どこかで「えいっ」ってなっちゃう心の弱さ、魔が差す感じで、この自殺未遂騒動のシーンは乗り切れるかなと。
そういう風に、現代のお医者さんの常識と照らし合わせて、物語に反映させるようにしていきました。