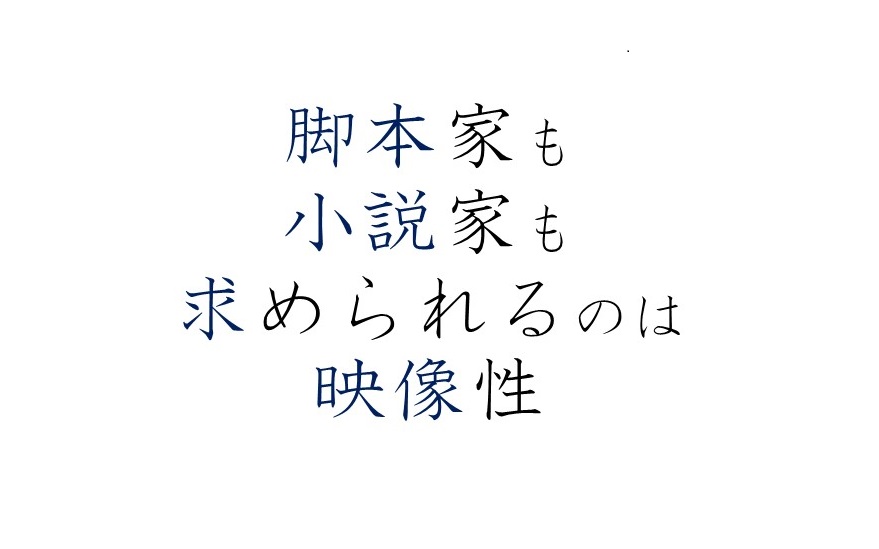発想から20年かかった理由
映画『舞妓はレディ』の企画が生まれてから、こうして公開するまでに、20年以上の時間がかかりました。
そもそもなぜ舞妓を題材にしようと思ったのか……。
『ファンシィダンス』、『シコふんじゃった。』と、2本続けて日本の伝統文化の中の男の子の話を描いたんですが、それなら今度は、女の子が伝統文化の中で活躍するというのはどうだろうと考えました。
そんな折に、京都の花街で舞妓のなり手が少なくなっているという話を聞き、舞妓という職業があるじゃないかと思い付きました。「そうだ、京都行こう」ですよ(笑)。
舞妓といえば、だらりの帯で京都の街中を歩いている可愛くて美しい白塗りの女の子という漠然としたイメージしかないまま、とにかくお茶屋さんを訪ねるというところからスタートしました。
一見さんお断りの世界ですから、いろいろなツテを辿って、お座敷をいくつか回ってみたわけです。
なぜ20年かかったか。お座敷を取材して、その世界のあり様というのがおぼろげながらに見えてくると、「これは、わかる訳ないな」と感じました。
禅宗の修行僧や学生相撲だって、深い意味では理解するのは大変だとは思いますが、とにかく見た瞬間から面白い。面白いから取材をしたのですね。ところが今回は逆で、舞妓という発想が先にあって見に行ったわけです。
お座敷に、仕出し屋さんから懐石料理が届き、芸妓さんと舞妓さんが来て、軽くお話ししながらお酒を飲み、ご飯を食べ、しばらくすると舞妓さんや芸妓さんが踊るのを見て、ちょっと喋ってお開き。「これの何が楽しいんだ?」って……(笑)。
初めての場所だし、取材だし、こっちは硬くなって緊張している。向こうもどう対応していいか分からなかったのかもしれませんが、ちょっと困ったなと思いました。あの世界のすごさや面白さを僕自身が感じられなかった。
そうしているうちに『Shall we ダンス?』を思いついてしまって、そっちに行っちゃったんです。
今でも覚えていますが、山形の酒田で、「舞娘株式会社」という、若い女性を募集して舞妓さんに仕立てて派遣するという会社組織があると聞き、取材に行ったんです。
その道中のこと。僕は同行したスタッフに、『Shall we~』のプレゼンをしたんです。もう完全に舞妓より社交ダンスの方に気持ちが行っていたわけです。ということで、最初の舞妓さんの映画化の機会を逸してしまいました。
その後、取材という形ではなく、純粋なお茶屋遊びに僕を誘ってくれる人が現れて、時々京都へ行くようになりました。そうしたら取材の時とは違って、いろいろな体験をすることが出来たんです。