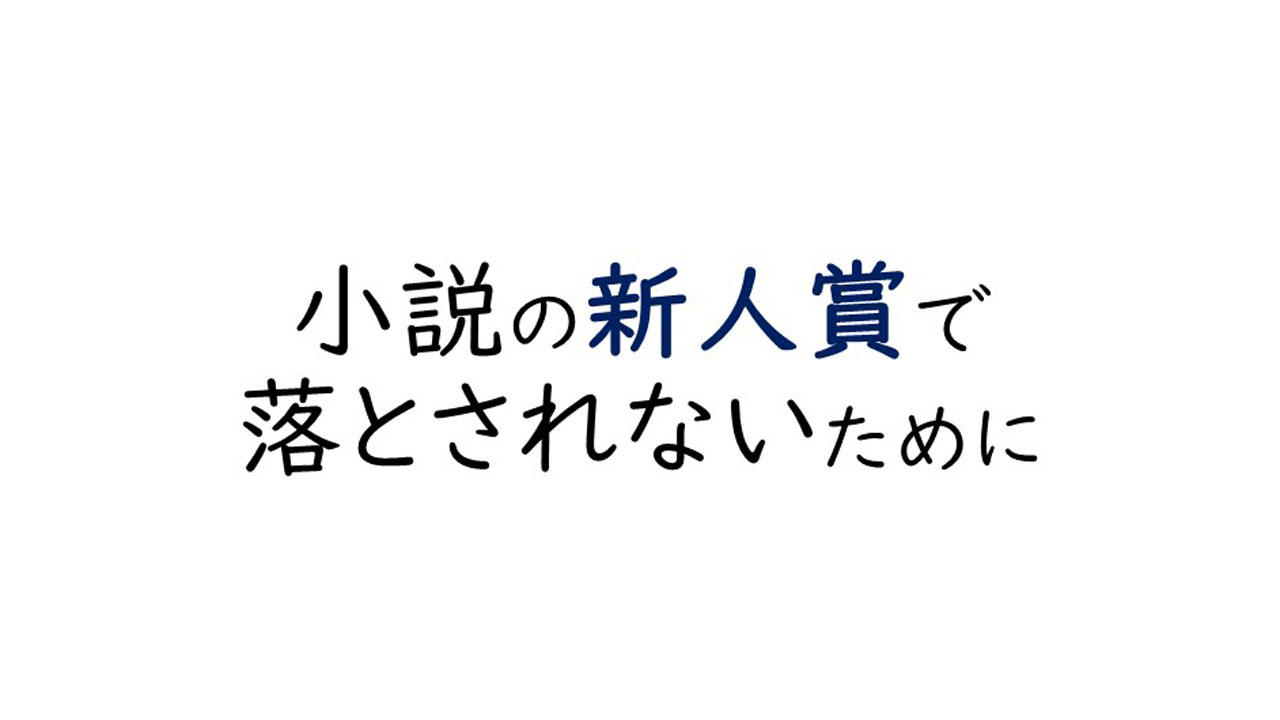辞書作りをどう見せていくかとか、作品の裏テーマに関しては僕が考えて、謙作さんは人間ドラマを作ることに力を注いでいました。
今回に関してはプロットもハコ書きもなかったですね。謙作さんからいきなり初稿が渡されたという形でした。僕自身は今回ほとんど脚本は書かなかったんです。一度謙作さんの筆が止まった時に、「僕ならこうする」というような、シナリオにもなっていないようなものを書いて渡したことはありますが。
それでも大体20稿くらいまでいったかな。決定稿になるまでに、かなり変わりました。
第1稿では、辞書作りの工程とか人物のキャラクターがよく見えなかったですね。最初は馬締と香具矢のキスシーンとかありましたよ(笑)。でも、そういうことじゃないんじゃないかなぁって。
つまり、今回は言葉の話だということもあり、肉体的な接触が重要なポイントになると思っていました。馬締と西岡が無駄にボディタッチを繰り返すちょっとアブない感じは、狙いでやっています。
逆に馬締と香具矢の接触は、最後の1回だけでいいと。あの夫婦は、あまり向き合わなくていいんじゃないかと思っていたんです。横並びで同じ方を見ているという。普通の恋愛ではなくて、あの2人はお互い自分のやりたいことに向かって進んでいる中での結婚ですから。……というようなザックリしたヒントを謙作さんに言うと、「なるほど」と面白がってくれましたね。
途中、物語が15年くらい飛びます。その間のことを描かないのには意味があると思ったので、原作の通りにしました。ただし、前半と後半の分量の比率には結構悩みました。
僕は29歳なので、馬締がどのように辞書作りに人生を捧げ、傾倒していくか、その姿こそ重要だと思っていました。対して謙作さんはちょうど15年後の馬締に近い年齢なので「いやいや大切なのは後半だろう」と。
僕が6対4、ないしは7対3でもいいと話したら、謙作さんは「違う、5対5だ」。撮影後に編集してみたら2時間40分以上あったので切っていったんですけれども、切ったのはほぼ後半のシーンでした。これは僕のエゴイズムかもしれないですが。
馬締が辞書の編集に関わるようになって、いろいろ恋も絡んで、ようやく舟を漕ぎ出す。その15年後に辞書編集部に入ってくるみどりという人物は、馬締が一度経験したことを繰り返しているんです。
映画的には終わっていることなんですよね。みどりの立ち位置は難しく、最初は原作に引っぱられて分量を多くとったんですが、馬締の目線で映画を通してみたら、余分に感じた。ですから、この部分をかなり削ることになりました。
僕はあまり取材が好きな方じゃないので、辞書編集部には1回しか行ってません。時間があまりなくて急ピッチで脚本を作っていたので、同時並行でロケハンをして。現場で脚本を変えたところは、ほんのちょっとはありましたけど、現場で変わるのはマズい脚本だと思います。
色々な方法を試してもいいけれど、最終的には脚本に戻っていけるような、そんな脚本を作ることが重要です。自主映画の時は、まったく逆のことをやってましたけど、あの時は自分に脚本能力がなかったってことなんじゃないかと思います。
今回初めて自分以外の人が書いた脚本で撮ったわけですが、やってみて、自分が書かない方がいいと思いましたね。他の人が書いたとしても、電話したり会ったりして、僕自身も十分に納得した上でホンが出来ているわけですから。
「こういう考え方もあるんだ」「こういう目線もあるんだ」という発見があって、自分にとって糧になったし、面白かったです。中には自分でホンを書かないとダメだという監督さんもいるかもしれませんが、僕はその辺はあまり気にしないです。
また、今回は自分にとって初めての原作ものでもありました。多少は、原作者の気持ちを考えますね、人間として当然の感情として。でも、自分の全能力と才能を出し惜しみせずに出す、という意味では、オリジナルも原作ものも同じです。
自分で脚本を書く場合は、必ずハコを立てます。結構緻密に作るほうです。PCで、例えば「馬締、辞書について悩む」とか「西岡が馬締をちょっと見直す」というように1行ずつ柱をバーッと書いていきます。全部書いて流れを決め、その間を埋めていくという作業。そうするとシーンの骨がわかりやすくなるので、とっちらからないんです。
物語の構造やアイデアについては、プロデューサーをはじめ、周りの優秀なスタッフたちが相談に乗ってくれるので、僕は自分にしか出せない作品のテーマを大事にしています。
※You Tube
Asmik Ace 映画『舟を編む』予告編より