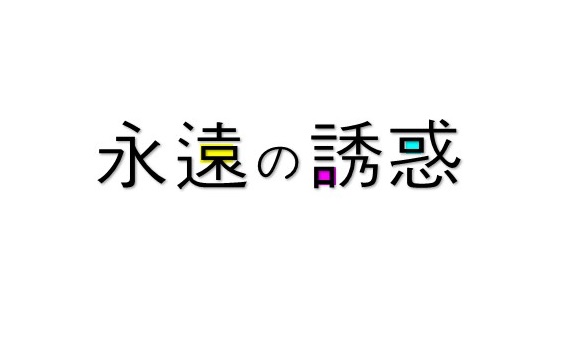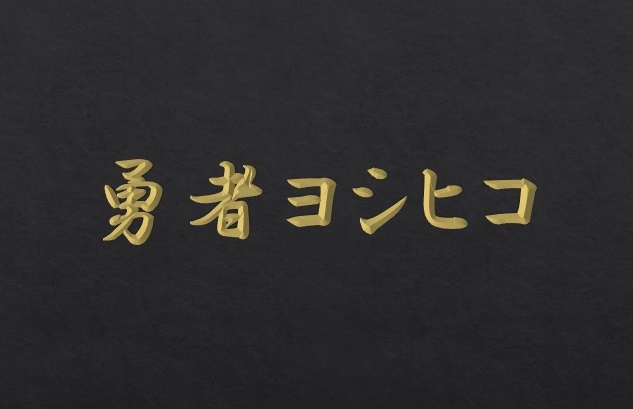『ファンシイダンス』と『シコふんじゃった。』
――桝井さんが映画作りを志されたのはいつ頃からですか?
学生時代、映研にいたわけでもなく虚しい日々を送っていたのですが、唯一映画だけが心の支えで、たくさん観ていました。
たまたま大映の企画部員募集の新聞広告を見つけ、「映画会社もいいかな」なんていう、割といい加減な気持ちで就職しました。
当時の大映は旧作をVHSにして売ることがメインで、新作を撮ることなど、ほとんどなかった。それに、大映が過去に製作してきたクオリティの高い作品に並んで映画を作るなんて、能力のない自分たちには無理だと思っていたんです。
――『ファンシイダンス』や『シコふんじゃった。』など、マイナーな題材を映画になさっています。
私の劇映画の最初のプロデュース作品は『ファンシイダンス』です。
周防正行監督作品で、漫画原作のものです。今と比べて、漫画の映画化をやるプロデューサーってそれほどいなかったんですね。競争率が低かった(笑)。
周防監督は研究熱心な方ですから、すぐに若い修行僧の取材を始めました。
ちょうどその頃大映は大作を製作中で、皆の意識がそちらに向いていた。この企画を通すためには、伊丹十三監督に出演してもらおうと考えました。
伊丹監督はヒットメーカーですから、会社に「オイシイ」と勘違いさせる作戦です。そうして企画を通したものの、伊丹監督に断られてしまった(笑)。代わりに奥様の宮本信子さんに出ていただくことになりました。
以前はそんな風に成り行きで成立していたんです、今は違うと思いますがね。
――主役に本木雅弘さんをキャスティングした経緯は?
私は当時「どうして自分が面白いと思っているモノが世に出ないんだろう」というフラストレーションを抱えていました。今までにないものを作りたかった。だから『ファンシイダンス』という企画をやろうとしたんですね。
主役はお坊さんですから、頭を剃らなきゃいけない。美形な男性を集めて坊主頭にしてズラッと揃えれば、ビジュアル的には面白いだろうと考えていました。
美形と言えば本木くん。彼はちょうど役者として新たに頑張ろうとしている時期でした。本人に直接オファーしたところ快諾してくれ、頭も剃りますと言ってくれた。お互いのタイミングが合った良い出会いだったし、僕もモチベーションが上がりましたね。
しかしこの作品はあまりヒットしなかった。興行成績としては失敗でした。僕は日本中が坊主ブームになると確信していたんですが(笑)、幻想でした。僕らのやっていることは世間的にウケないという挫折感がありました。
でも、周防監督やモックンと一緒に仕事をするのは楽しかったので、『ファンシイダンス2』をやりたいと。ところが会社側は「Vシネマなら作っていい。ただし予算は半分だ」。僕はサラリーマンなのに意地を通してその話を断りました。別の企画で会社をギャフンと言わせようと、やる気が湧きました。
『ファンシイ~』原作の岡野玲子さんは様々な方面にアンテナを張っている方で、「次は絶対にお相撲さんが来るわよ!」とおっしゃる。僕らにとっては神の啓示のような感じでした(笑)。
調べてみると、相撲の映画って、あまりなかったんです。「どんなに出来が悪くても、世の中の相撲映画の5本のうちの1本にはなるだろう」なんて、保険のように考えていました(笑)。
早速両国界隈の取材を始めたところ、当時、相撲の世界は非常に敷居が高かった。国技館での撮影なんて、もってのほか。プロの世界を撮るのは難しいと気付いた。
そこで監督の母校である立教大学の相撲部を取材することにしました。キリスト教系の学校なのに相撲部の奥に神棚があるし、相撲部員たちは皆痩せていて、「なんでこの人たちが相撲やっているの?」という感じで笑っちゃう。
女の子にモテるわけでもない。それでも彼らは一生懸命やっているんです。そこに感動したし、シンパシーを感じました。
『シコふんじゃった。』っていうタイトルは、単なるダジャレですよね。私もかなり抵抗したんですが、周防監督は結構こういうのを面白がる方で。
立教大学に「『シコふんじゃった。』っていう映画で」とロケ交渉したら、ふざけていると思われて、断られたんです(笑)。なので、あれは老人ホームを借りて撮影しているんですよ。
――自分の気持ちが「面白い!」と反応したものを映画にしているのですね。
映画というのは、当たるか当たらないかの保証がまったくない世界です。たまたま企画が通って、たまたま結果がついてきたという感じですね。
映画会社に勤めていると、「映画は当たらない」と刷り込まれるわけです。会社からは「映画を作るな。映画なんか作らない方が身のためだぞ」と言われる(笑)。
リスクがあるし、失敗すれば会社に損害を与えるからです。テレビ局が企画を買ってくれるなら話は別だが、自社で製作するのはダメだよと。
『シコふんじゃった。』は映画賞も獲って、評判は良かったのですが、興行的には回収できなかった。ヒットするかどうかと作品の評判は、メカニズムが違うのかもしれません。
会社の限界も感じましたし、映画の企画って本当に難しいなと実感しました。
――『シコふんじゃった。』の翌年に大映を退社されたのですよね?
これもまた志の低い話なんですが(笑)、会社が傾いて希望退職者を募ったので、退職金が上乗せされるならいいなと思って辞めたんです。
だからといって独立して何とかなる時代でもなかった。会社にいてもフリーになっても、どっちにしろ同じだったんです。
ただ、独りでやっていく根性もなかったので、周防監督と磯村一路監督を誘って会社を設立しました。東京乾電池オフィス社長だった小形雄二さんが、「うちの事務所に机を置いてもいいよ」と言ってくださったので、そこで居候生活を3年くらいやっていました。
――お聞きしていると、地獄を楽しんでいらしたような感じですが(笑)。
いえいえ、全然楽しんでない(笑)。流れに身を任せていただけです。親切な方々が周りにいらっしゃったから。それで1年くらいしてから『Shall we ダンス?』の企画を立ち上げました。