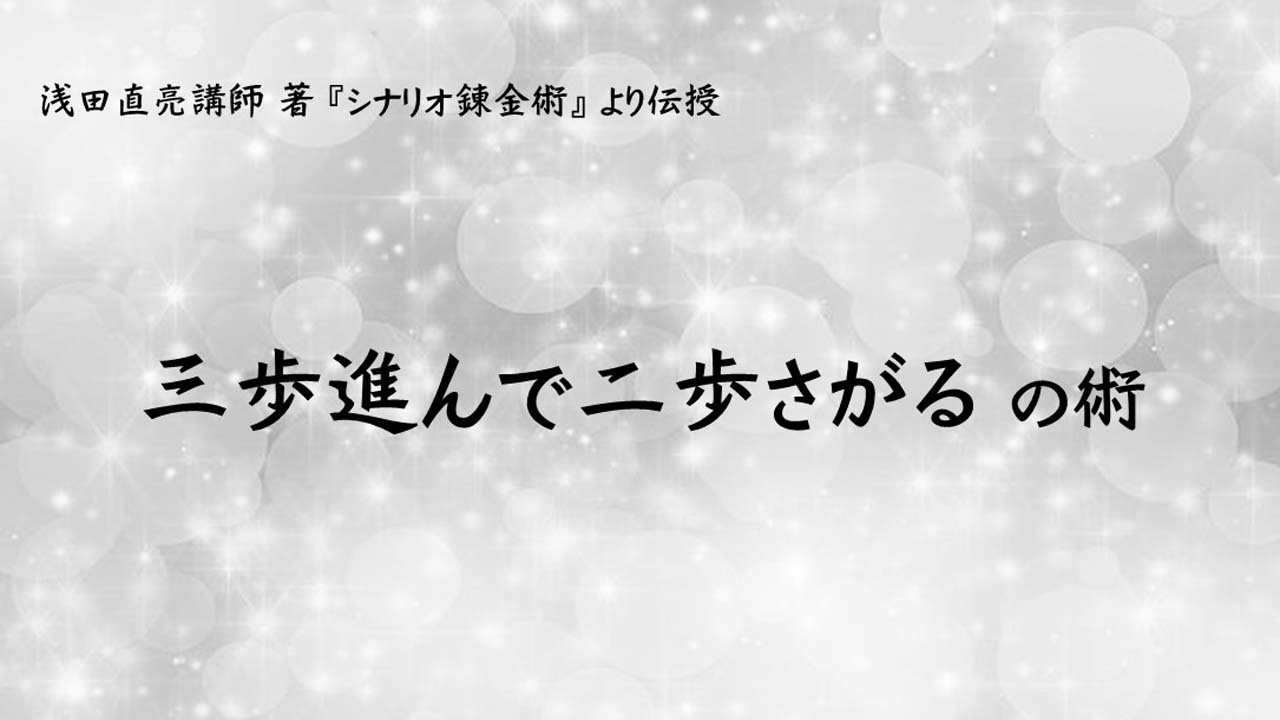シナリオ・センターでは、ライター志望の皆さんの“引き出し=ミソ帳”を増やすために、様々なジャンルの達人から“達人たる根っこ=基本”をお聞きする公開講座「ミソ帳倶楽部 達人の根っこ」を実施しています。そのダイジェスト版を『月刊シナリオ教室』(今回は2018年9月号)から。
今回は、ドキュメンタリー映画『ヨコハマメリー』と『禅と骨』を手掛けた中村高寛監督にお越しいただいた模様をご紹介。「ドラマ(フィクション)を作りたいから、ドキュメンタリーには興味ない」という方はこちらの記事で発見することが大量にあると思います。ドキュメンタリー制作の過程には、面白いドラマを作るヒントが沢山あります。
ゴールを決めるか決めないか
私が映画『ヨコハマメリー』のためのリサーチを始めたのは22歳の時です。それから2年後の24歳でカメラを回し始めて、公開したのは31歳の時です。22歳で作り始めて31歳で劇場公開したので、結局9年かかっている計算です。
皆さん驚かれますが、実は2作目の『禅と骨』も9年近くかかっています。33歳の時に主人公のヘンリ・ミトワさんと知り合って、昨年公開した時、私は42歳だったので、これも公開までに9年かかっている……。9年に1本の監督になりつつあるので、このスパイラルをなんとか脱しなくてはまずいと思っています(笑)。
私はテレビのドキュメンタリーの仕事も時々しますが、「中村監督がやるんだから、きっと長くかかるんでしょ」みたいなことをよく言われます(笑)。
でもNHKのドキュメンタリー番組枠「ハイビジョン特集」の1時間半のものだと、撮影から放送までだいたい3ヶ月か4ヶ月くらいで作ったこともあります。ルーティンというか、ある方法論に則ってこういう風にやれば撮れますよ、ということも知っているし、その経験もあることはあるんです。
ところが自分の映画となると、ちゃんと時間をかけてやりたい。ドキュメンタリーの映画とテレビの違いで明確に言えるのは、ゴールがあるかどうか、つまり終わり方ですね。ゴールを決めるか決めないかだと思います。
『ヨコハマメリー』は、主人公であるはずのメリーさんが、終了間際の5分間しか出てこない。基本的にはメリーさんと関わった人たちへの取材を中心に構成しています。オーソドックスなドキュメンタリーだと、ある登場人物がいて、その対象者の人となりを追っていく、その人の歴史みたいなものを紐解いていきます。
なぜこんな作り方になったかというと、取材し始めた時には、メリーさんはもう街にいなかったからです。これで果たして映画が成立するのか?リサーチしている時も、主人公がいなかったら映画にはならない、作品化できないよって、よく指摘されていたんですが、ふと考えたんです。
発想の転換をして、もしもドラマだったらこういうのってよくあるよなと……。ある人物が失踪して、周りの人たちがその人物を物語ることによって、いなくなった人の輪郭みたいなものが浮かび上がってくるような対象不在の話って結構あるよな、それはドラマとして成立するよなって思ったんです。
私が元々ドキュメンタリー畑でなく、ドラマの助監督だったからこそ生まれた発想かもしれません。
知らないからこそ見つけられる新しい視点
私はどんな題材、お題がきても作品化できると思っています。今回だとハマのメリーさんが主人公ですが、実質的な主人公はシャンソン歌手の永登元次郎さんだったりします。
次の『禅と骨』だと日系アメリカ人の禅のお坊さん。このお坊さんも、京都では有名かもしれませんが、全国的な知名度は決して高くはないんですね。それでも私が全然、映画として作れますよ!と言えるのは、要するに対象者のどこに興味を持って、どういう視点で撮ればいいのかが見えれば作品化できるという確信があるからです。
その確信が生まれるようになったのは、『ヨコハマメリー』を撮ったからです。横浜に、常盤とよこさんという有名な女流写真家の方がいらっしゃいます。その方は戦後の横浜、まだ進駐軍がいる横浜を撮られている方で、これは蔑称ですけども、いわゆるパンパンと呼ばれた女性の方たちにカメラを向けた方なんです。私がその人に取材を申し込んだ時に「あなたに何が分かるの?彼女達のこと何も知らないじゃないの、あなたいくつなの?」と言われました。
確かにそうだなと。私は1975年生まれで、メリーさんや戦後生き抜いてきた人たちの気持ちがどれほど分かるのかと……まあ分からないわなあと、全く反論できませんでした。
その時は非常に落ち込んで、自分にハマのメリーさんが描けるのか?確かに自分はメリーさんと同じ時代を体験していないと自信喪失したんです。でもよくよく考えみると、体験していた人しかその時代、歴史が描けないなら、ある意味で歴史というのはそこで終わってしまい風化していくだけだ。語り継ぐことなどできない。
逆に自分は何も知らないからこそ、新しい視点を見つけられるんじゃないか。そして新しい視点を得られた時に、初めて自分の作家としての個性が出るんじゃないかと思いました。
なぜ自分は撮るのか、歴史的な題材を目の前にして、自分の視点は何なんだと考えたわけです。そのことを意識して撮っていき、自分の視点が絞れた時に、作家としての自分の核が見つかったという実感がありました。
リサーチで当時の生活を追体験
『禅と骨』には、ウエンツ瑛士さんと余貴美子さんが出ているドラマパートがあります。主人公のヘンリ・ミトワさんが、昭和15年真珠湾攻撃が始まる前年に、自分のお父さんを探しにアメリカに渡るんですが、その前の日本でのお母さんとのやり取りを、ドラマパートとしてまとめています。
その時に一番最初にやったのは、昭和15年の新聞を元旦1月1日から12月31日まで、1枚ずつめくって読んでいって、自分が気になるところをメモしていくという作業でした。
実をいうとその前後の昭和14年や16年のあたりもずっと読んでいます。それが実際のセリフの中のちょっとした会話で生かされることがあります。何よりもその時代を自分の中で追体験したくて、その中で登場人物がどう動くのかを想像しながら、ずっと読んでいきました。
そのやり方がシナリオ作りにおいて有効かどうかというのはわからないですが、私の場合は大きなトピックだけをメモするわけではありません。
当時の新聞を読むと、当時流行った映画が載っていたり、また昭和15年だったら、日本でお米の配給制が始まったとか、細かい生活の匂いを感じるところがいっぱい出てくる。まずそこからその世界に入っていくことが私にとっては大事なことで、その時代を生きている人たちの生活の匂いみたいなものを感じたいと思って読んでいきました。
ドキュメンタリーでも物語性を作ることができるんじゃないか
『ヨコハマメリー』を撮り始めた時には、まず元次郎さんであるとか、写真家の森日出夫さんなど、メリーさんとの関わりのあった人たちをちゃんと記録するんだという、記録性みたいなものを重視していました。
しかし撮影途中から、私のなかで大きな変化がありました。何が変わったかというと、撮っている最中に、元次郎さんに癌が見つかった。
そこから話がどんどん動き始めていくというか、映画がどんどん監督である自分の意思とは関係なく、登場人物によって動かされていったんです。その時に「あっ、これってドラマのようだな」って思いました。ドラマにおいて役者が演じているキャラクターが、それぞれが動いていくような感じがしたんです。
記録だけではなく、ドキュメンタリーでもナラティビティ、いわゆる物語性を作ることができるんじゃないかと、パッと閃いたんです。そこから元次郎さんの闘病などを軸にして、あるストーリーラインが作れるんじゃないかと思い、この映画の全体像が固まってきました。もちろん私自身、物語性を意識して撮るようになりました。
撮影を始める前に、私は取材対象者へのリサーチをすると言いましたが、『ヨコハマメリー』では、撮影開始前の2年間、映画に関係する市井の人たちと会って、関係を築いた上でカメラを回しています。
例えば元次郎さんのシーンなどは、1999年に最初のインタビューを撮った後、2年間くらい撮影はしていません。でもその間も元次郎さんに会いに行って世間話しながら、元次郎さんの幼少期の話とか、お母さんへの想いなどを聞いたり、普段何をやっているのか聞いていくわけです。
それを基にしてカメラを実際に回した時には、こういうことをしてくれるんじゃないか、プラスアルファで、こういうことを想定できるんじゃないかと、シーンリストとして書いておくわけです。
「たら、れば」でも、これは起こるかもしれないということを、カメラを向けながら試していく。でも実際そうならないことも多い。それもドキュメンタリーの面白さです。
勿論、役者を使ったドラマじゃないから、私が指示を出せるわけじゃないし、実際まったく違った反応になるときもある。それも含めてシーンリストを書いていって、全く的外れだったとしても、それすらも面白がって、また別のシーンとして撮っていく。それを繰り返していくのが、私が思うドキュメンタリーの醍醐味だと思います。
『禅と骨』では、主人公のヘンリ・ミトワさんとそのご家族が全員集合するシーンがあります。息子さんはアメリカに住んでいるんですが、奥さんを連れて帰ってきて一家団欒のシーン。そこで家族がもめ始めるんですが、あれは想定外でした。
もともと私が考えていたシーンは、アメリカ在住の息子さんが京都にやってきて、家族が何年かぶりに一堂に会します。ミトワさん自身、高齢なので、今回が家族で集まれる最後になるかもしれない。その晩餐を撮りたいと思いました。
まず私から「こういうシーンはどうですか?」とミトワさんに提案をして「それはいいね!」ということで設定したシーンです。ところが全く想定外のことが起こってしまった。
面白いのは、家族というのがこの映画では大事なテーマになるだろうと思っていました。まだ確信はないながらも、私がそのことを意識していたからこそ生まれたシーンだったのです。何も考えずに目の前のことを撮っているだけだったら、何も起こらなかったと思います。私がシーンの意味、作品のテーマを追い込んでいく中で化学変化が起こっていった、ということです。
先ほど、シーンリストを作ると言いましたが、そもそもその前にシノプシスを作るんですね。その上でシーンリストを書き出していって撮っていく。自分の中で想定して『ヨコハマメリー』ならこういうストーリーにしたい。『禅と骨』だったら、ヘンリ・ミトワさんの人生のなかでも、この部分を強調したストーリーにしたいと決めて撮っていくんですね。
でもそういう風に考えていても、そのまま撮れてしまうと、それは面白くないわけです。何かしら想定外のことが起こったほうが面白い。どんなプラスアルファがあるのかを期待しながら撮っていくんです。
カメラを向ける側と向けられる側の境界線
さきほど登場人物によって動かされていると言いましたが、実際に撮影前に事前リサーチを行い、私が「こういう人だろう」と想定していた以上に、カメラを向けていくと登場人物がどんどん動いていく。そうなると監督である私自身も映画の中の一員になっていく感覚があります。
『ヨコハマメリー』も、完成した後に時々、見直すと「このシーンはどうやって撮ったんだろう?」というシーンがいっぱいある。映画の後半になっていくと、自分ではない「何か」に撮らされているような感覚になっていく。
映画ではあくまでも裏方、監督という役割ですが、自分自身も登場人物の1人として、その空間というか、時間軸の中で一緒に生きて動いている感覚に陥っていくんです。カメラを向ける側と向けられる側の境界線がだんだん曖昧になり、それがなくなった時に初めて自分にとって納得いくシーンが撮れているんだと思います。
『禅と骨』を撮っている時も同じ感覚になったんですが、どうやったらそうなるのかはわからない。きっかけも、いつ動き始めるかも、いつ撮らされている感覚になるのかもわからなくて、ただひたすら登場人物、そしてテーマを追っていくことしかない。これが方法論として使いこなせたら、もっと多作の作家になれると思いますが……。
プロットは撮影途中での書き直しはしません。完成した映画の縦軸は、ほぼ最初に書いたプロットのとおりなんです。だからこそ時間をかけてリサーチをして、骨子を固めたいんです。そのあと新しい事実が出てきたり、人物が動いたりしても、一番大きな縦軸だけは作っておく。そこを固めた段階でクランクインの瞬間が来ると思っています。
『ヨコハマメリー』は300時間くらい、『禅と骨』は400時間の収録素材があるんですけど、撮影が何年も続いていくと、自分の中で分からなくなることがあるんです。自分がどんな映画を撮ろうとしたのかを見失いかけた時に、必ず最初に書いたシノプシスをもう1回読み直すんです。
その時に、「元々、自分がやりたかったのはこういうことなんだよな」っていう原点を確認する。それは編集作業に入った時にも必ずやります。
インタビューの文字起こし作業
ドキュメンタリーにおける構成の話に入る前に、文字起こし作業について話しておきます。インタビュー素材が2時間とか3時間あると、これを全て文字に起こしていきます。
所謂、テープ起こしとも言われる作業です。それをプリントアウトし、作品中で使いたいな、面白いエピソードだなと思ったところにマーカーを引いていきます。そしてそのマーカーを引いた箇所を抜粋して、組み合わせていく。その後、実際の映像を見て繋げていく、編集作業をしていきます。
これを全ての登場人物の素材で行い、本編で使う部分を決めていく。マーカーを引くときの基準となるのは、説明的ではなくて、その人の感情が出ているところですね。
ドラマでいうところのセリフの部分をピックアップしているともいえます。どこの箇所、セリフを使えば、その登場人物を最も的確に表すことができるのか?ということを精査していく。
通常、人間の話す言葉は、そんなに理路整然とはしていないので、セリフを前後、入れ替えたりして、ちゃんと話として通じるようにしていきます。時には1、2時間ほど話してもらっても、2分くらいしか使えないこともザラにあります。
でもこれが完成した映画を観た時にグッとくるんですよね。その人物の一番核心ともいえる言葉、つまりセリフを導き出せた時には、ドキュメンタリーはやめられないって思います。
この時、私が気をつけているのは、登場人物に複数のことは語らせない、1つのトピックがあったら、そのことについて絞り込んで話してもらう。つまり登場人物がどういう意思を持って、何について語っているのかを明確にしていくことが重要になります。
この文字起こしに関して言うと、私はもともとVシネマとかオリジナルビデオ、「土曜ワイド劇場」などの2時間ドラマの演出部にいたんですね。その仕事をルーティンでこなしている時にふっと、役者のセリフがまったくリアルに感じなくなってしまったんです。
「この人はどういう気持ちで言っているんだろう。そこにどんな感情がのっているんだろう」と、ずっと現場にいながら違和感があったんです。じゃあ「本当にリアルなセリフって何なんだろう? 何を話せばその人にとってリアルになるんだろう」っていう疑問が生じてきました。
その当時、どこまで意識的だったかはわかりませんが、ドキュメンタリーの世界に入っていったきっかけとして、人間が話す言葉のリアリティとは何なのか?を知りたかったんだと思います。
いまドキュメンタリー作っていて、登場人物たちの言葉を紡ぐようになってからは、ドラマの脚本を読むと面白いんですね。「あっ、この言葉は全く生きていない。ただ表層的だなあ」「この状況で、人はこんな言葉の使い方はしない」とか、セリフの意味を考えられるようになりました。
付箋を使って構成を考えていく
カメラを回す前に撮影項目を考え、シーンリストを作ります。そして登場人物の状況やスケジュールに合わせて、それらのシーンを撮っていくのです。
まず最初に作ったシーンリストをほぼ撮り終えた段階で、それらのシーン1つ1つを付箋で書いていき、ホワイトボードにストーリーの流れに合わせて貼っていきます。これはハコ書のようなものだと思います。
付箋は色分けをして、例えば黄色は主人公が実際に画に映っていて、取材を受けたりしているところ。黄緑が資料写真とか資料映像。灰色が友人知人や関係者の人、つまり脇役みたいな人たちという分け方をしていきます。
『禅と骨』は、この作業をクランクインから1年後にしました。撮影予定のシーンは赤の付箋で、これが第2次シーンリストになっていきます。そして撮り終えると、付箋の色が赤から黄色や灰色に変わっていくのです。
構成を練っていくうちに、使い道が分からなくなったシーンは、取りあえずボートの端に貼っておきます。構成とはシーンとシーンの組み合わせなので、これからの話の流れ、この後に撮れたシーンとの組み合わせで使えるかもしれない。今のところは、まだ端に置いていますが、敗者復活戦もあります。
撮影を行う度に、付箋の位置を入れ替えて、構成を考えていくと、また赤の付箋がどんどん増えていきます。それが溜まっていくと、第三次シーンリストの出来上がりです。
これを時間をかけて、繰り返しているうちに赤の付箋がほとんどなくなっていくのですが、その時こそ「編集に入るタイミング」ということになります。
ただドキュメンタリーの場合、私がお願いしても先方の事情で撮れない、ということもあるので、撮れないならば、その代替として何が撮れるんだっていう構成を考えていきます。
常に動いていく構成を考えながら台本作りをしている感覚かもしれません。事実、ピクチャーロックすると同時に、ドキュメンタリー用の台本も完成させます。でもここまでやっても、シノプシスは変わらないんですね、不思議なことに。
もしかしたら何か起こるんじゃないかと“種を蒔く”
横浜から居なくなったメリーさんの近況は、当初まったく知りませんでした。事前リサーチしているうちに、メリーさんの故郷は分かりましたが、その時、彼女がどこにいるのかは不明でした。それでメリーさんという対象不在のドキュメンタリーという手法でクランクインしたのです。
映画を見てわかるように、メリーさんのスキャンダラスなところを暴くというよりも、メリーさんを通して横浜を描くことに主眼をおいています。
それが撮影を始めて1年が経ったときに、メリーさんの居場所が分かってしまったんです。故郷からそう遠くない老人ホームにいました。困ったんですよね、対象不在なのに見つかってしまった(笑)。
仕方なく取材目的ではなく、メリーさんに会いにいきました。ホームの方には、「元次郎さんや白新舎の山崎ご夫妻など(メリーさんとの)共通の友人がいるので、彼女の様子を見に来た」と伝えて、ずっと通っていました。ところが3週間くらい通っていたら、ムクムクと湧いてくるわけです、撮りたい!っていう気持ちが。
まあ思いますよね、でも撮っても使えないなとも思いました。いきなりワイドショーみたいに押し掛けて行って、これが今のメリーさん!って撮っても仕方ないし、誰も見たくないだろうなと。どうすればいいかわからずに、結局、悩んでいるだけで答えはでなかったんですけど、種を蒔くことにしたんです。
それまで横浜の人たちはメリーさんがどこにいるか分からなかった。そこで映画に出演してもらった元次郎さんや森日出夫さんなどに、いまのメリーさんの暮らしを報告しにいったんです。
もしかしたら何か起こるんじゃないかと、そんな淡い期待を抱いていましたが、勝算はありませんでした。これが僕にとって種を蒔くという作業です。メリーさんに想いのある人たちだったら、何かを呼び起こすんじゃないかと思ったんです。
そして種を蒔いた1年後くらいに、元次郎さんから電話がかかってきました。
映画のゴールが見えた瞬間
元次郎さんに会いにいくと、メリーさんと再会したというんです。会ってきたと。何でも、メリーさんの老人ホームの近くでコンサートをやったので、その帰りに立ち寄ったそうです。
メリーさんもすごく喜んだみたいで、「元次郎先生の歌を聞きたいわ、今すぐ歌ってくれないかしら」と言って、コンサートの帰りということで、ちょうどピアニストもいたので、元次郎さんも快諾したんですが、ホーム方からイベントをやるんだったら事前申請が必要だと言われたそうです。
「歌えなかったのよ、でもそれからメリーさんからも手紙が届いて、できればチャンスがあったら歌いに行きたいのよね」と、元次郎さんから聞いたときには「やったぜ!」と思いましたね(笑)。蒔いた種が育っていたんです。
その後、元次郎さんに癌が見つかると「最後のチャンスかもしれない」と、彼の付き添いとしてホームに一緒にいきました。その時に撮ったのが、最後のシーンです。実はその時は、それこそ記録として撮ろうかなって思ったんですね。対象不在のドキュメンタリーを作っているという意識は変わっていませんでしたし、たとえ撮ったとしても、どう使うのかは想定していませんでした。
でも最後、元次郎さんが歌う『マイウェイ』を撮ったときに、この映画は、これで終われるって、ふっと思えたんです。確かに対象不在のドキュメンタリーだけど、これを入れないと終われないなって。まさに映画のゴールが見えた瞬間でした。
一部のドキュメンタリー関係者からは、この映画は破綻していると指摘されます。対象不在でやっているのに、何故、最後の最後に出てくるんだと。まあそうなんですよね。
でもどんなに破綻があろうと、あのシーンを入れないと、この映画は終われないだろうと思ったんです。先ほど、私は撮らされている感覚があるという言い方をしましたが、この時も自然と映画がラストを決めてくれたということです。
横浜を通して日本の近現代史を見つめる
私は横浜出身で、ハマッ子にとってメリーさんは伊勢佐木町にいくと必ず見かける存在、ある意味では日常だったんです。私は映画を撮る以前はメリーさんを見かけてはいたけど、話したことはなかった。
逆に興味を持ち始めたのは、メリーさんがいなくなってからなんです。ずっと街角に立ち続けていた人なので、みんなメリーさんを知っているんですよ。だけど噂話では色々と好き勝手に言うけれども、本当のことは誰も知らない。
私もずっと見かけてきたのに、あの人って一体何だったんだろう?というのが最初の疑問でした。これは映画が完成した時に思ったんですが、横浜で生まれ育った人のことをハマっ子と呼びますが、私の世代では横浜に対する地元意識ってそんなにないんです。
横浜を出ると、周囲から「ハマっ子だろ」と言われ「自分にとっての横浜って何なんだろう、自分が育ってきたこの町って何だろう?」って思っていました。そんな時にメリーさんを通して、上の世代の人たち、まさにハマッ子たちに話を聞いていくと「横浜ってこういう街なんだよ。こういうことがあってさ」と、私が今まで住んできた横浜って、こういう街だったのかという発見がたくさんあったんです。
つまり自分にとっての故郷や地元とは何かを探す作業を、映画を通してやっていたんだと、今になって思います。また最初、撮り始めたときは考えていなかったことですが、撮り進めていくうちに、自分は横浜を通して日本の近現代史を見つめ、描いていきたいんだなと思うようになりました。それは『ヨコハマメリー』だけでなく『禅と骨』でもそうですね。
横浜は日本の開港と同時に、常に歴史の表舞台に立ってきたとも言えます。逆にいうと、横浜の歴史、変遷を見ていくと、日本の近現代が象徴的に見えてくるんです。なので、この横浜という街を通して、近現代の日本とは何だったのか?というのを、自分なりに考えていきたいんです。それが映画という媒体で、どう成立するのかを考えながら撮っています。
例えば『禅と骨』は横浜の映画だと自分では思っているんですけど、主な舞台は、ミトワさんが住んでいた京都なんです。でもミトワさんから横浜の話を聞いていると、京都にいるにも関わらず、横浜の風景が、私の中にデジャブのように呼び起こされる瞬間みたいなものがある。時空や場所をこえて、記憶で繋がっているんですかね。
最近では、横浜でロケをして、横浜の風景を撮ったから「横浜の映画」ということではなく、横浜のメンタリティや記憶をどう描けるかと考えています。次の映画も横浜を描こうと思っているんですが、横浜の風景は1回も出てこないかもしれません。それでも横浜の映画だって思えるものを作りたいですね。
1パーセントのために
『ヨコハマメリー』は2006年に公開されたあとも、細く長く上映は続いています。ちなみに中国では、日本のドキュメンタリーでとても有名な作品になっているらしいです。
公式上映は3回だけなんですが、海賊版が出回っているらしく、今年3月に北京に行ったら、喫茶店のウェイトレスの方も知っていました。そうやって国をこえて、徐々に浸透していくのは、監督冥利に尽きますね。
これからも自分のやりたいことに対して、ただただ正直に映画を作っていきたいですね。基本、自分で制作費をほぼ出していますし、スタッフも少人数なので「まだ撮りたい、まだ終われない」と思ったら、自分が納得いくまでエンドレスで撮り続けられる。それが私流のドキュメンタリーの強みです。
時々、映画監督をしているというと、とても華やかな世界にいるんじゃないかと思われるんですが、そんなことはありません。図書館に通って資料を読み込んだり、ひたすらパソコンに向かって文章を書いたり、また構成を考えたり、インタビューの文字起こしをする毎日です。
実際この生活をしていて楽しいことなんてほぼありません(笑)。100%とは言いませんが99%ない。唯一1%は完成した時です。初号試写の時の安堵感、そして達成感。また公開初日を迎えた時、大勢の観客に観てもらった時の、あの瞬間を味わったら、もうやめられない(笑)。
99%辛くても、たとえ毎日が地味で退屈でつまらなくても、その1%のために頑張ろうと思ってしまう世界です。
皆さんも自分のやりたいことやテーマが何かひとつでもあれば、苦しくても頑張ってください。
〈採録★ダイジェスト〉THEミソ帳倶楽部「ドラマを面白くするドキュメンタリーからのヒント」
ゲスト:中村高寛さん(映画監督)
2018年5月19日採録
★次回は6月29日に更新予定です★
プロフィール: 中村高寛(なかむら・たかゆき)
1975年生まれ。1997年、松竹大船撮影所よりキャリアをスタート。1999年、中国・北京電影学院に留学し、映画演出、ドキュメンタリー理論などを学ぶ。2006年に映画『ヨコハマメリー』で監督デビュー。横浜文化賞芸術奨励賞、文化庁記録映画部門優秀賞、ヨコハマ映画祭新人監督賞・審査員特別賞、藤本賞新人賞など11個の賞を受賞。2017年監督第2作目映画 『禅と骨』(シナリオ・センター出身 林海象監督プロデュース)が公開。
“最初は基礎講座から”~基礎講座コースについて~
映像シナリオの技術は、テレビドラマや映画だけでなく小説など、人間を描くすべての「創作」に応用することができます。
そして、ドキュメンタリー映画を作るときも、シナリオの技術は使えます。
まずはこちらの基礎講座で “土台”を作りましょう。
■シナリオ作家養成講座(6ヶ月) >>詳細はこちら
■シナリオ8週間講座(2ヶ月) >>詳細はこちら
■シナリオ通信講座 基礎科(6ヶ月) >>詳細はこちら