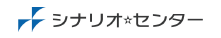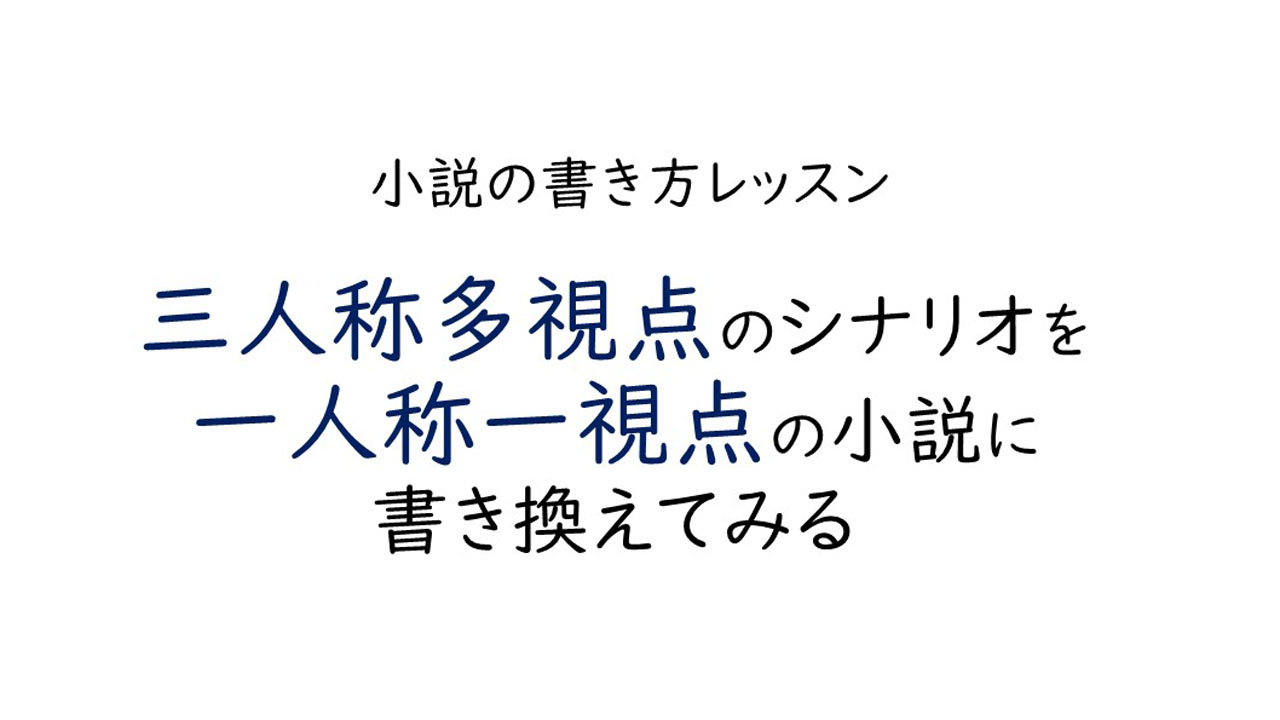シナリオ・センターでは、ライター志望の皆さんの“引き出し=ミソ帳”を増やすために、様々なジャンルの達人から“その達人たる根っこ=基本”をお聞きする公開講座「ミソ帳倶楽部 達人の根っこ」を実施しています。そのダイジェスト版を『月刊シナリオ教室』よりご紹介。
今回の達人は、作家の石井光太さん。取材対象の中に自らを置いて一緒に生活することによって、対等の目線で、現実を切り取っていくという石井さん独自のスタイルをお話頂きました。
“普通の”ノンフィクションライターは語らないことをルポルタージュに
僕は物心つく頃から創作を仕事にして生きようと思っていました。創作といっても、映像は多くの人が関わるから自分の思いが叶いにくい。本だったら95%は自分の好きなようにできると思い、文章を書こうと決めました。
それが高校生の時です。文章が下手だったので、1日に3冊は本を読み、1週間に1冊は手で書き写していました。プレゼントも全部図書券にしてもらっていて、だからバレンタインもチョコではなく、図書券。
そして18歳の時にパキスタンとアフガニスタンに行きました。パキスタンでは物乞いの障害者が道端にズラーッと並んでいた。僕はその時、この人たちの日常を書いたら絶対にうまくいくと確信しました。
手足のない物乞いの人を見たら、普通のノンフィクションライターは世界平和を語ろうとする。
でも僕は、その人がどうやってウンコしてるんだろうとか、その人はそもそもどうやってこの道端にやって来たんだろうとか、奥さんはいるんだろうかとか、そういうことに興味と疑問を持ったんですね。
それで、彼らのことを1~2年追ってルポタージュを書き、それが僕のデビュー作になりました。
「根拠のない自信」「違和感」「環境づくり」の3要素をもつ人
=うまくいった人
うまくいった人というのは、みんな「根拠のない自信」「違和感」「環境づくり」の3つの要素を持っています。
「根拠のない自信」というのは、100%うまくいくと思えるかどうかということです。一瞬でも迷ったら、うまくいかない。僕だって迷っていたら、彼女からのプレゼントを図書券にしていない。もうこれは理屈じゃない。
それから「違和感」。僕はすべてのことに対して違和感を持っています。今こうして皆さんの前で喋っていることに対しても、自分がノンフィクションを書いていることに対しても、です。
書いているヤツって、基本的に上から目線になる。じゃあどうやったら、取材相手の本音を聴けるのか。そりゃ、一緒に暮らすしかないですよ。
その当たり前のことをやったら、「新しい」と評価された。でもそれにも違和感を持ちました。違和感を覚えた時に、何をするかが作家の個性です。自分が感じた違和感を形にすることで作品になる。
「環境づくり」は、自分がやりたいことを実現させるためには何が必要か。例えば僕が津波の取材で宮城に行きたいとします。そのためにはお金が必要だし、書いた記事を載せる枠もないと困る。
そこで僕はある週刊誌の編集長に連絡を取りました。僕は20~30人くらいの編集者と親交があります。普段からアイデアをパーッとぶつけて、種をまいておくんです。ノンフィクションというのは取材ありきですから、膨大なお金と時間が必要になります。
すぐにうまくいく場合もあれば、いかない場合もある。その中で、いざという時に「石井に書かせよう」と思ってもらえるような関係を作っておく。
何を面白いと思い、それを面白く書けるかどうか、
相手に魅力を感じられるかどうか、を大切に
皆さん、知らないうちに固定概念にとらわれていませんか?
一番重要なのは作家性であり、アイデアです。奇抜なこと、というよりは、何を面白いと思い、それを面白く書けるかどうか。
たとえば、死刑制度について書いてと言われたとします。普通は裁判員制度とか、人権とかそういう話になりますよね。僕はそういうのはどうでもいい。
死刑台、あれを作っている会社って絶対にありますよね。それもたぶん一流の建設会社じゃないかな。そこに就職したごく普通のサラリーマンがですよ、死刑台の設計をしなくちゃいけなくなる。
他国の死刑台を視察しに行ったり、首縄の素材選びとか、はたから見たら、くだらない議論の末に開発している。もしかしたら家族にも内緒だったりするのかもしれない。
僕はそっちの方が普通に知りたい。本屋に「裁判員制度」って本と「死刑台のつくり方」って本が並んでいたら、どっちを買いますか?
そういうことです。どれだけ突き抜けられるか、自分に正直でいられるか、それが作家の視点と個性につながるのだと思います。
よく訊かれるのは「豊かさとは何か」。でも豊かさがどうとかには興味ないし、知ったこっちゃない。僕が取材する上で大切だと思っているのは、相手に魅力を感じられるかということです。
映画『スラムドッグ・ミリオネア』にも描写されていましたが、スラムで、マフィアに手を切り落とされたり目を潰されたりして、物乞いをしている男の子たちに会いました。手がなかったり、目が見えない方がいくらか多くお金をもらえるからです。
僕は最初「そんなことをしたらイカン」とマフィアに反感を持っていました。ところが、男の子たちはかばうんです。「パパをいじめないで」と。「あなたは僕に何かしてくれた? 何もしてくれない」と。
彼らにとってマフィアとは、一緒にご飯を食べ、一緒に寝てくれる大切な存在なんです。僕はその瞬間、彼らのことを美しいと思いました。僕はそれを「小さな神様」と呼んでますが、もしかしたら、それが彼らにとっての豊かさなのかもしれない。
人間なんて100%矛盾した存在だし、みんなが社会的に正しい文脈の中で生きている訳じゃない。それを認めることが重要じゃないかと思います。
自分の価値観を壊されたときに、正直に認めて、それを面白いと思えるか。何か違和感を持った時に、あらかじめ作られたストーリーにはとらわれず、元にある真実を探して作品にできれば、読者も面白がってくれるはずです。
僕は、会った人みんながうまくいってほしい。シナリオライターを目指している人には、ちゃんとシナリオライターになってもらわなきゃ困る。そうじゃないと今日話した意味がないですからね。1分1秒も惜しんで、人生を楽しみましょう。
出典:『月刊シナリオ教室』(2011年6月号)より
〈採録★ダイジェスト〉THEミソ帳倶楽部「ノンフィクション作家の根っこ惨状でなく日常を描く」
ゲスト:石井光太さん(作家)
2011年3月28日採録
プロフィール:石井光太(いしい・こうた)
1977年東京都生まれ。 国内外の文化、歴史、医療などをテーマに取材、執筆活動を行っている。 ノンフィクション作品では、アジアの障がい者や物乞いを描いた『物乞う仏陀』やイスラームの性や売春を描いた『神の棄てた裸体―イスラームの夜を歩く』、その他『絶対貧困』『遺体』『浮浪児1945-』『「鬼畜」の家』『43回の殺意』『本当の貧困の話をしよう』『こどもホスピスの奇跡』『近親殺人』など多数。小説・児童書・エッセイ・漫画原作など幅広いジャンルで活躍。
【要ブックマーク】その他のゲストの講座もチェック!
基礎講座コースについて
今回こちらの記事をご覧になって「文章を書いてみたい!」と思われた方は、まずは基礎講座から、お気軽にご参加ください。映像シナリオの技術は、テレビドラマや映画だけでなく小説やアニメ・マンガ原作など、人間を描くすべての「創作」に応用することができます。こちらの基礎講座で、書くための“土台”を作りましょう。
■シナリオ作家養成講座(6ヶ月) >>詳細はこちら
■シナリオ8週間講座(2ヶ月) >>詳細はこちら
■シナリオ通信講座 基礎科(6ヶ月) >>詳細はこちら