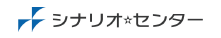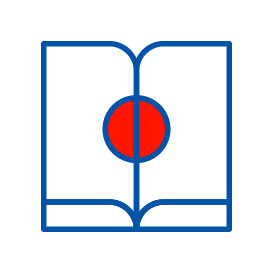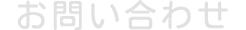シナリオ・センターの新井がお手伝いさせていただいている、昭和女子大学×世田谷区立下馬図書館×図書館総合研究所「VIVITA BOOKS 世田谷ふしぎの本プロジェクト 2025」。
2023年・2024年・そして今年の模様(※)もリポートしております↓
※今年の模様はこちらから。
▼発想を飛ばすにはマインドマップ@世田谷ふしぎの本プロジェクト2025
このプロジェクトは、子どもたちが作家役、昭和女子大学の学生たちが編集者役となり、「feel度walk」(=なんとなく気になるモノ・コト・ヒトと“出遭い”ながらあてもなく歩くこと)で見つけた“不思議”をテーマに、下馬図書館に来る子どもたちや地域の方々に読んでほしい絵本を作り上げるプロジェクト。作品は完成後、下馬図書館の本棚に並びます。
先日、担当の笹川さん(図書館総合研究所)より、このようなご相談をいただきました。
<完成した絵本の巻末に掲載している「編集後記」の“リニューアル”を考えています。
プロジェクト開始当初、編集後記はなかったのですが、読者の方々から「このストーリはどうやってできたのか」「どういうところが大変だったのか」「絵本ができあがるまで、このペアはどう変化・成長したのか」といった“水面下のこと”を知りたいというお声を沢山いただき、掲載するようになりました。
一応、書き方の“型(カタ)”はあるのですが、年々伝えたいことが増えてきて、アレもコレもと詰め込み過ぎた結果、中途半端な感じになっているような気がしています。
今回から他のスタッフも編集後記を書くことになったので、これまでとは違う“新たな型”を決めたいのですが、どうしたらいいかなと……>
ということで、世田谷ふしぎの本プロジェクト2025の編集後記を担当されるスタッフの皆さんに向けて、シナリオ技術を使って問題を解決する「エンタメシナリオ」を実施させていただくことに。
その模様を広報の齋藤がリポートいたします。
「編集後記ってどう書けばいいんだろう?」とお悩みの方、是非参考にしてください。
“伝えたい相手”が沢山いる場合、絞らなくても大丈夫?!
そもそも編集後記とは、書籍・雑誌・社内報などの最後に編集者やライターが書く「あとがき」。内容は、制作の裏話や感想、読者へのメッセージなどさまざま。主に読者に向けて書かかれるが、制作に関わった関係者への感謝を伝える場合もある――というもの。
この“そもそも”を踏まえて、新井が皆さんにお聞きしました。
「一般的な編集後記は主に読者に向けて書かれていますが、この絵本の場合も“伝えたい相手”は読者ですか?」
すると、スタッフの皆さんから、
①作者であるペアの2人にも伝えたい
②作者以外のペアの人たちにも伝えたい
③次回このプロジェクトの参加を検討している方にも伝えたい
④世田谷区民の方にも伝えたい
――という意見が挙がりました。
そこで新井、はたと気づきます。
〇新井:あ!そっか。一般的な編集後記とはちょっと違って、この編集後記の場合は、
読者だけでなく①のように「この絵本の作者」に向けても書きたいし、
「読者」と一言で言っても②③④のように「読者のタイプ」がいろいろあるんですね。
〇スタッフの皆さん:そうなんです!だから、①~④の中から、誰に向けて書くのかという“伝えたい相手”を1つに絞りこむのは難しいです……。
〇新井:そうですね、分かりました!絞り込まなくて大丈夫です!
――え!!!と、わたくし齋藤、叫びそうになりました。
シナリオ・センターが実施している「キッズシナリオ」や「シナリオ研修」では、動画や映画のシナリオを作るにせよ、小説を作るにせよ、作品のジャンルに関わらず、「伝えたい相手によって、伝える内容が変わってくるので、作品のテーマを誰に伝えたいのか、伝えたい相手を“ひとり”具体的に決めてください」とお伝えしています(※)
※その模様はこちらで。
▼地域の魅力を伝えよう!PR動画づくりのポイント@横浜市立菅田の丘小学校
また、伝えたい相手を絞ることで、伝えたいテーマがブレてしまうことを防ぐこともできます。
シナリオや小説と編集後記は勿論ジャンルは違いますが、でも、絞らなくて本当に大丈夫なのか!
とドキドキしていたのですが、新井がこう言うには訳がありました。
“この人にこう感じてほしい”という「目的」は違えど、
そのための「手段」はひとつ:それはキャラクター!
*
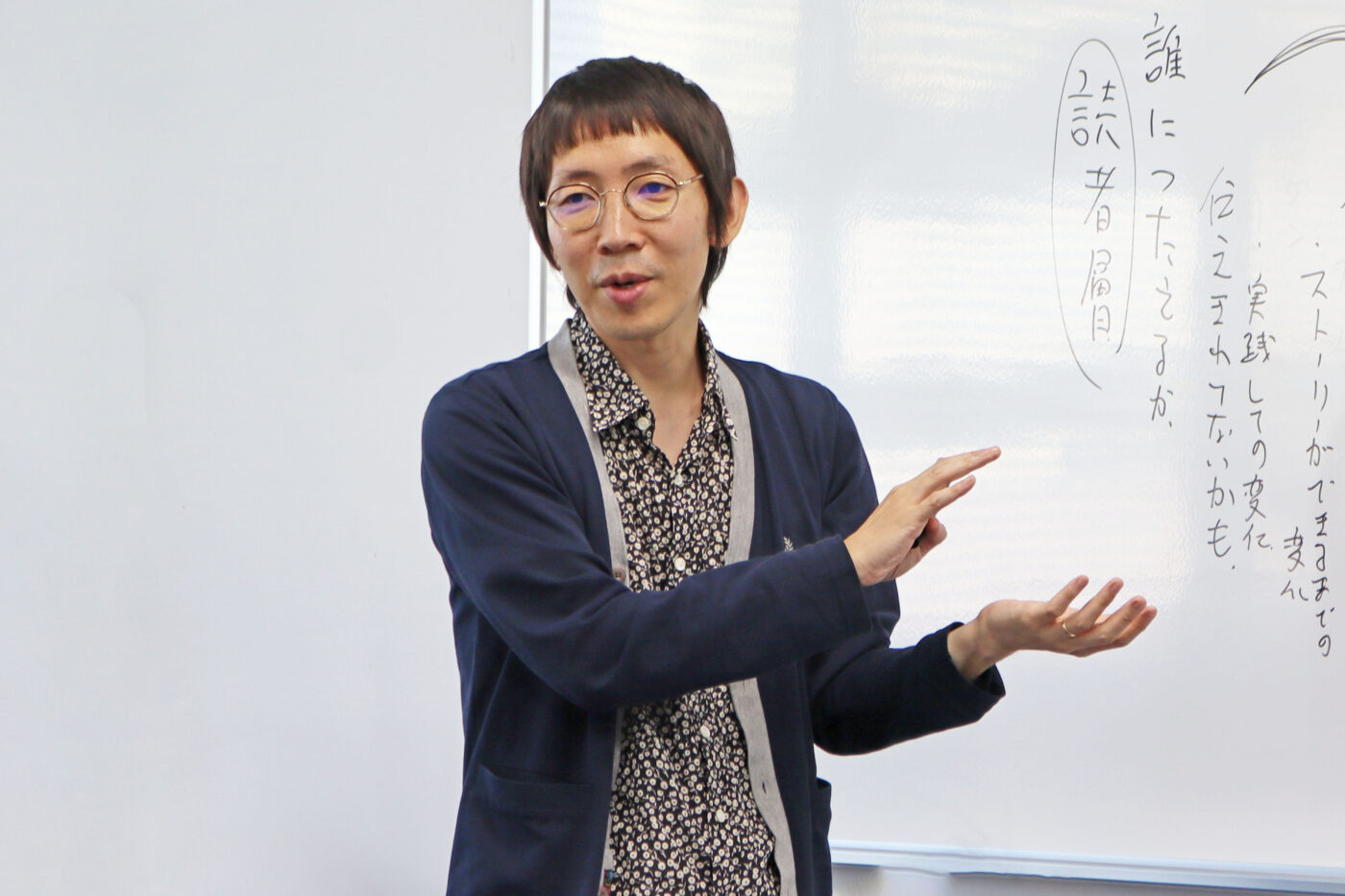
〇新井:この編集後記を読んで、
①の“作者であるペアの2人”には、「このプロジェクトに参加して良かった!」と思ってほしいですよね。
②の“作者以外のペアの人たち”には、「このペアはこんなふうに作っていったんだ!」と思ってほしいですよね。
③の“次回このプロジェクトへの参加を検討している方”には、「参加してみたい!」と思ってほしいですよね。
④の“世田谷区民の方”には「この街だからこそ作ることができた絵本であり、プロジェクトだな!」と思ってほしいですよね。
こんなふうに、一般的な編集後記とはちょっと違っていて、この編集後記の場合は“この人にこう感じてほしい”という「目的」がさまざまなんですよ。
でもね、「目的」はさまざまでも、「手段=やること」は1つなんです。
それは、ペアの2人がこの絵本を作るまでにどう変化・成長したのか、を記録すること。
この編集後記は「活動記録」なんです。
ただ、活動記録といっても、このペアはこんなことやあんなことをしましたという「出来事」を記録するわけではないんです。
記録するのは、このペアの「キャラクター(性格)」が出ている部分。
例えば、先ほど実施した授業(※)の大学生編集者さんを思い出してください。
あの大学生編集者さんは、feel度walkで見つけた「落ち葉」から「大の字の人→スカイダイビングを終えた人」とマインドマップも使わずに見事に発想を飛ばすことができました。でも、そこで満足はせずに、マインドマップを使って一生懸命考えていましたよね?
で、「落ち葉→葉っぱの形→スペード→トランプ→トランプが軍隊を作る→女王である“花”を守るために戦う」というまた違った見事なアイデアを短時間で考え出しましたよね?
キャラクターが出ているじゃないですか!
あの大学生編集者さんは、よく考えるキャラクター。
よく考えるキャラクターの人が今後、このプロジェクトを通してどう変化・成長するか。
気になりますよね!
もしかしたらですよ、例えば、よく考えるキャラクターのこの大学生編集者さんは、これまではいつも行動する前に必ず熟考していたけど、何かの作業のときに、敢えて考えずに直感で決めてみたことで素晴らしいアイデアが生まれた!なんてことが起こるかもしれない。
もしこういうことが起きたら、すごい変化・成長のエピソードですよね?
こんなふうに、大学生編集者さんや子ども作家の子のキャラクターを把握して、そのキャラが出ているエピソードを記録して、それを編集後記としてまとめれば、その人だからこその変化・成長を伝えることができるんです。
こういった内容ならば、“伝えたい相手”が
①の“作者であるペアの2人”の場合は、「そんなこともあったね!このプロジェクトに参加して良かった!」と思ってもらえるだろうし、
②の“作者以外のペアの人たち”の場合は、「このペアはこんなふうに作っていったんだ!知らなかった!」と思ってもらえるだろうし、
③の“次回このプロジェクトへの参加を検討している方”の場合には、「こういう変化・成長を経験できるんだ!参加してみたい!」と思ってもらえるだろうし、
④の“世田谷区民の方”の場合には、「こんなふうに作っていったんだ!この街だからこそ作ることができた絵本であり、プロジェクトだな!」と思ってもらえるはず!
どうですか、無理に“伝えたい相手”を絞らなくても、
大学生編集者さんや子ども作家の子のキャラクターが出た部分を記録するこの「手段」を使えば、
「こういうふうに感じてほしい!」という皆さんそれぞれの「目的」は達成できそう、ですよね?
――この新井の問いかけに、スタッフの皆さんから「はい!」「なるほど!」「このやり方なら目的達成できそうです!」「すごく腑に落ちました!」という感想をいただくことができました!
今回新井が提案した方法をご活用いただいて、ステキな編集後記を書いていただければと思います。
絵本の完成だけでなく、編集後記の完成も楽しみにしています!
※世田谷ふしぎの本プロジェクトの活動は、こちらのInstagramにて発信中。ぜひご覧ください↓
▼世田谷区立下馬図書館Instagram(@setagaya_shimouma_lib)
https://www.instagram.com/setagaya_shimouma_lib/
▼VIVITA BOOKS Instagram (@vivita_books)
https://www.instagram.com/vivita_books/
* * *
「編集後記ってどう書けばいいんだろう?」とお悩みの方の中には、今回ご紹介したように「伝えたい相手を絞りきれない……」という方もいらっしゃるのでは?
そんなときは、物語を書くときと同様、「キャラクターを描くこと」に着目してみてください。
例えば、何かお店を紹介したときの編集後記なら、その店主さんやお客さんのキャラクターに着目してみたり。もしくは、取材を通して自分が感じたことを自分のキャラクターを全面に出して書いてみる、というのも読者を惹きつける一つの手かもしれません。
こちらの動画は、物語をつくるときの「キャラクターを引き出すコツ」ではありますが、編集後記でキャラクターに着目するときのヒントにもなるかと思いますので、是非ご覧ください↓
▼【クリエイティブ】キャラクターを引き出すコツ
※今回ご紹介したようなシナリオの技術を使った授業や研修をいろいろな施設で実施しています。
こちらをご覧ください。
▼コミュニケーション力 を上げるシナリオ研修 事例まとめ
新井一樹 著書ご紹介
今回ご紹介した感情移入するポイントの他、「面白い物語を作る方法をもっと詳しく知りたい!」という方は新井の著書を是非。
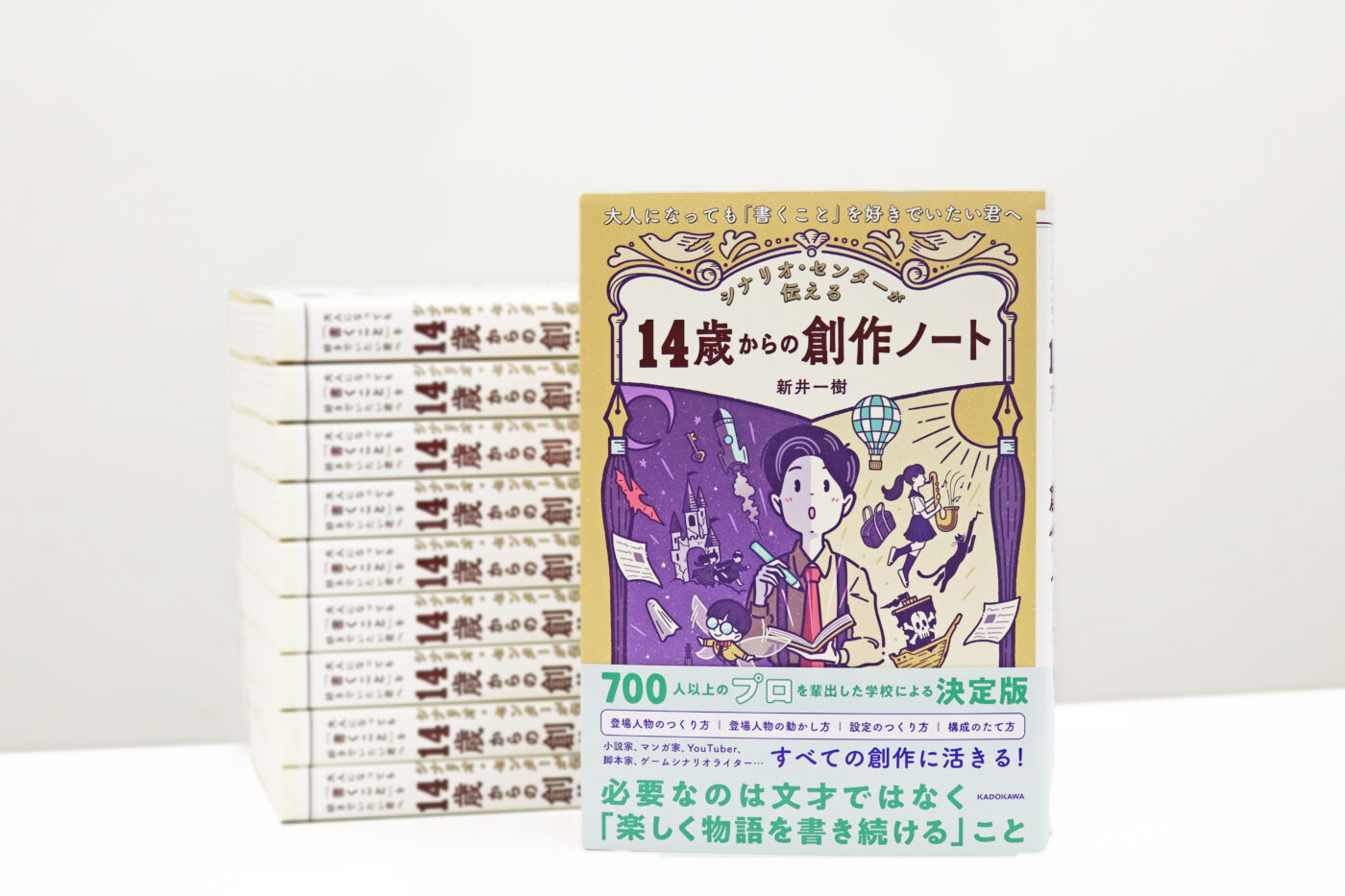
・2024年6月19日発売
▼『大人になっても「書くこと」を好きでいたい君へ シナリオ・センターが伝える 14歳からの創作ノート』(KADOKAWA)
Amazon販売サイト https://amzn.to/3V3WV3o
※こちらのブログも併せてご覧ください
▼あなたのアイデアを、物語に仕上げるための『シナリオ・センターが伝える 14歳からの創作ノート』
・出版記念イベントとして開催した特別講義「頭ひとつ抜けた小説を書くためのシナリオ・センター式 創作術」
▼【カクヨム】アーカイブ動画&書き起こし記事
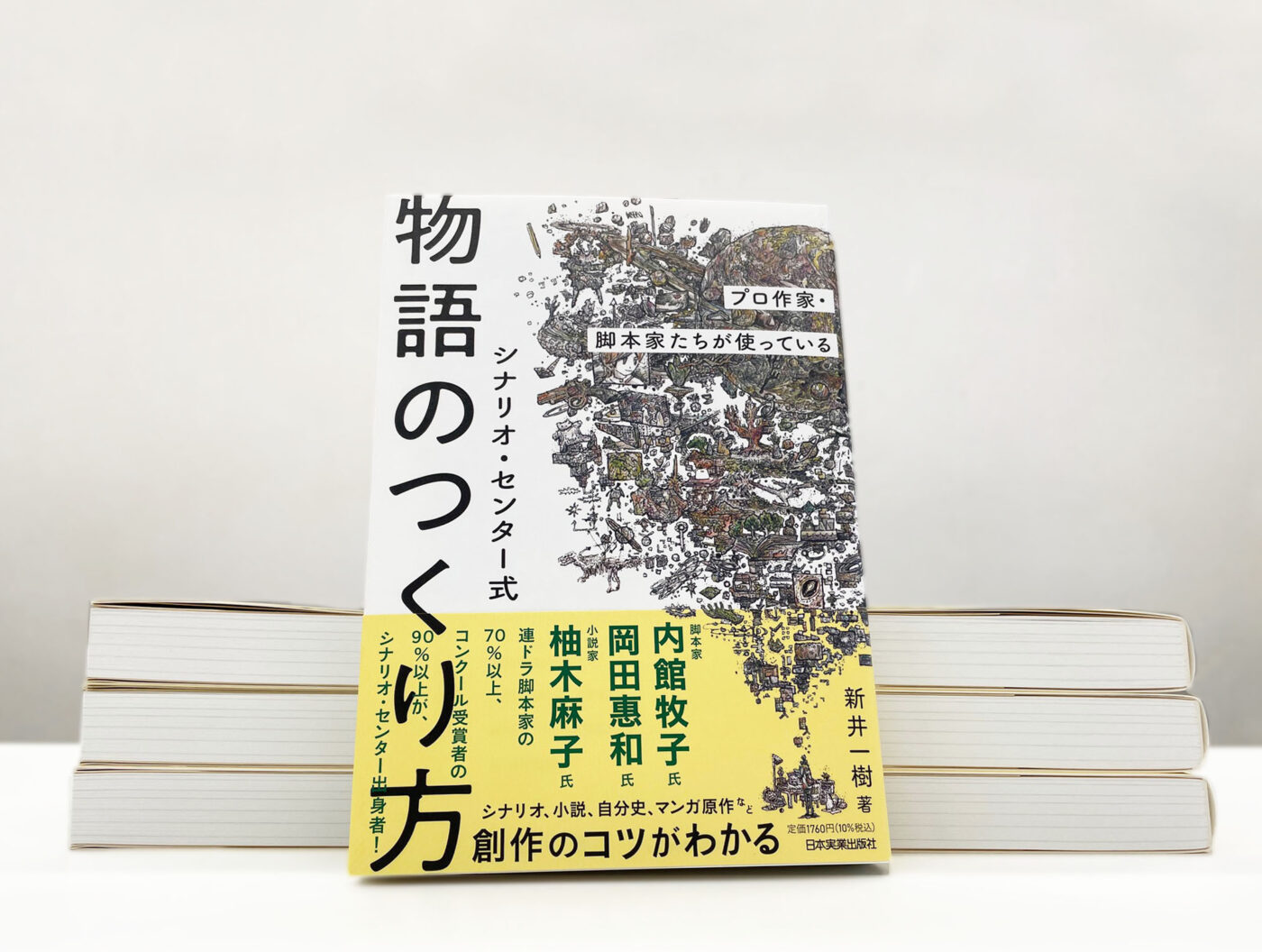
・2023年7月28日発売
▼『プロ作家・脚本家たちが使っている シナリオ・センター式 物語のつくり方』(日本実業出版社)
Amazon販売サイト https://amzn.to/3NTgA2p
※こちらのブログも併せてご覧ください
▼面白い物語になっているかチェック!『シナリオ・センター式 物語のつくり方』
「シナリオの技術に興味が出た!」tという方はシナリオ・センターのシナリオ講座で基礎を
映像シナリオの技術は、テレビドラマや映画だけでなく小説など、人間を描くすべての「創作」に応用することができます。
面白い物語を書く上で大切な表現技術が身につく基礎講座は、全部で3種類あります。
① シナリオ作家養成講座
②シナリオ8週間講座
③シナリオ通信講座 基礎科
期間や学び方に違いはありますが、どの講座もすべてカリキュラムはシナリオ・センター創設者 新井一著『シナリオの基礎技術』を基にしています。
「いきなり申し込むのはちょっと不安……」という場合は、無料で資料をご請求いただけます↓
また、シナリオ作家養成講座に向けた無料説明会や体験ワークショップ、シナリオ8週間講座に向けた体験ワークショップもございますので、お気軽にご参加いただければと思います。