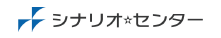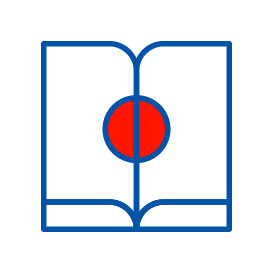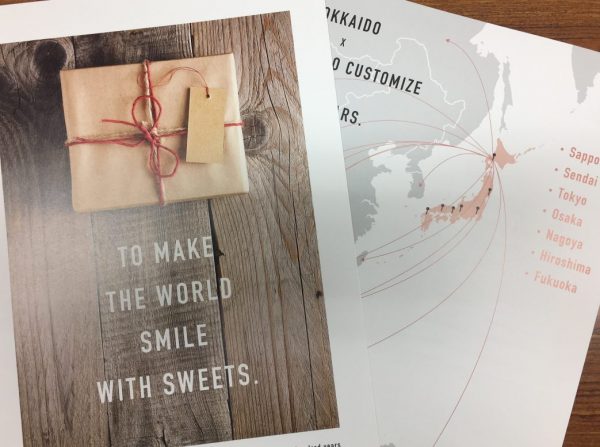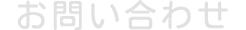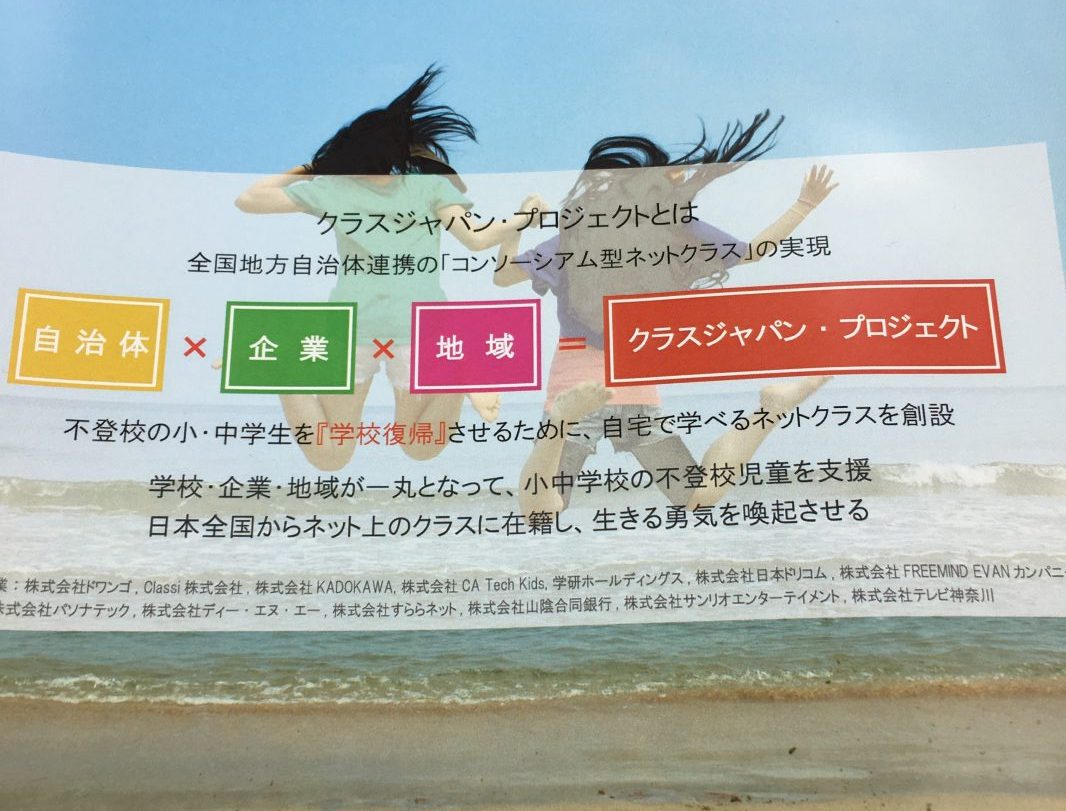自慢話は聞いてもらえない
会社案内や営業資料は、往々にして企業の自慢話になりがちです。それはそうです。「ウチの会社、信頼できますよ!」「ウチのサービス、すごいですよ!」と言いたいですから。
ですが、資料を目にする方々が、その説明に興味があるわけではありません。いや、むしろ、興味がない場合の方が多いわけです。
そんなお客様にでも、刺さる営業資料・会社案内を作ることは、誰でもできます。
以下のポイントに沿って、自慢話ではなく、お客様が聞きたくなる話しを作っていきましょう。
・シンプルに「何を伝えるか」を考える
・ターゲットを整理する
・起承転結を押えて情報を整理する
・出だしは、ターゲットの立場で考える
・「承」で問題を解決していく
・伝わる言葉にする
シンプルに「何を伝えるか」を考える
資料を作る際には、大きく二つのことを考えます。「何を伝えるか」と「どう伝えるか」です。どちらも共通するのは、お客様の立場で考えるという点です。
資料作りの「構成」を考える段階では、「何を伝えるか」だけで整理することがポイントです。
資料を作るとなると、どんな言葉で伝えるか、どんな図表を作るかなど、色々なことが気になってしまうのではないでしょうか。ここで「どう伝えるか」まで考え出すと、2つの作業に頭を使うことになります。これ、大混乱の元です。
なので、はじめは「何を伝えるか」だけを考えます。
ターゲットを整理する
「何を伝えるか」が出てきたら、次に確認したいのが、誰に向けた、何のための資料かということです。20代を意識するのか、40代なのか、男性か女性かなどです。
「そんなこと当たり前だ」と思うかもしれませんが、ターゲットを明確にすることはとても大切です。なぜなら、資料を作成する過程で、伝えるべき情報の取捨選択、伝え方までターゲットが基準になるからです。
ターゲットがぼんやりしてしまうと、全ての情報がぼやけてしまいます。
起承転結を押えて情報を整理する
資料作りで一番迷うのは、伝えたいことをどういう順番で伝えればいいのか、ではないでしょうか。順番を考える際は、ターゲットのとなるお客様が資料を読み終わったときに、どんな気持ちになっていればいいかを考えます。読み終わりのお客様の気持ちから逆算して、乗せるべき情報を考えることができるからです。
まず考えるべきは、起承転結の「転」になります。「転」では、こちらが伝えたいテーマを伝えます。次に考えるのは「結」です。「結」は、テーマの定着と余韻という機能があります。
「転」で、こちらが伝えたかったテーマが伝わり、「結」は、お客様が「確かにそうだな」と思っている状態になります。
実際の内容はこちら「北欧、暮らしの道具店」を運営するクラシコムさんでの事例>>「BRAND NOTE PROGRAM」にフィットする営業資料作り をご覧ください。
出だしは、ターゲットの立場で考える
「転」「結」が決まったら、出だしを考えます。ドラマの構成では「起」にあたります。「起」で考えるべきことは、テーマに対するアンチテーゼです。アンチテーゼというのは、テーマの逆という意味です。
「テーマ」で伝えたいことが「便利だよ」だとしたら、「アンチテーゼ」は「不便な状態」になります。出だしも、お客様にどんなアンチテーゼがあるのかを考えます。
お客様自身の問題意識に働きかけることができれば、自ずと興味を持って資料を見てくれます。
「承」で問題を解決していく
「起」と「転」「結」の関係は、逆になります。
この逆の状態を、変化させるのが「承」の機能です。お客様が抱える問題の解決策や解決に至る根拠を「承」で提示していきます。
構成については、「結」を意識するだけで、 伝える 力が変わる も参考にしてください。
伝わる言葉にする
伝えるべきことが整理されたら、あとは「どう伝えるか」というクリエイティブを練っていきます。文言やレイアウト、デザインなど、練りに練る段階です。ここでは、各自の好みが出てきます。
ですが、構成の段階で「何を伝えるか」が定まっていれば、お客様により伝わりやすい言葉、デザインをのびのびと考えることができます。
実際に、大手菓子卸問屋さんの海外進出のための営業資料の作成を、担当の方々と一緒に行いました。ドラマの「構成」を意識して作り込み、デザインに落とし込むことで、アジア圏のスーパーマーケットのバイヤー担当が集まる展示会では、多くの商談を得ることができました。
感動は、万国共通です。ドラマの「構成」は、世界でも通用します。
営業資料・会社案内を作成する際には、是非、起承転結を意識してくださいね。