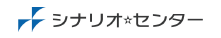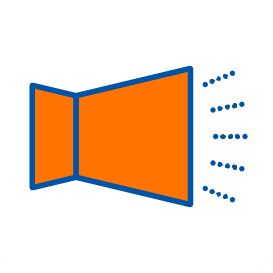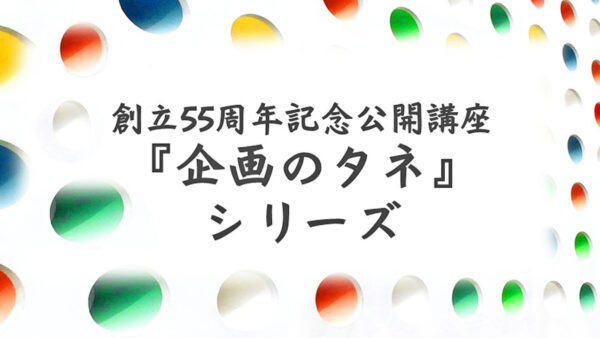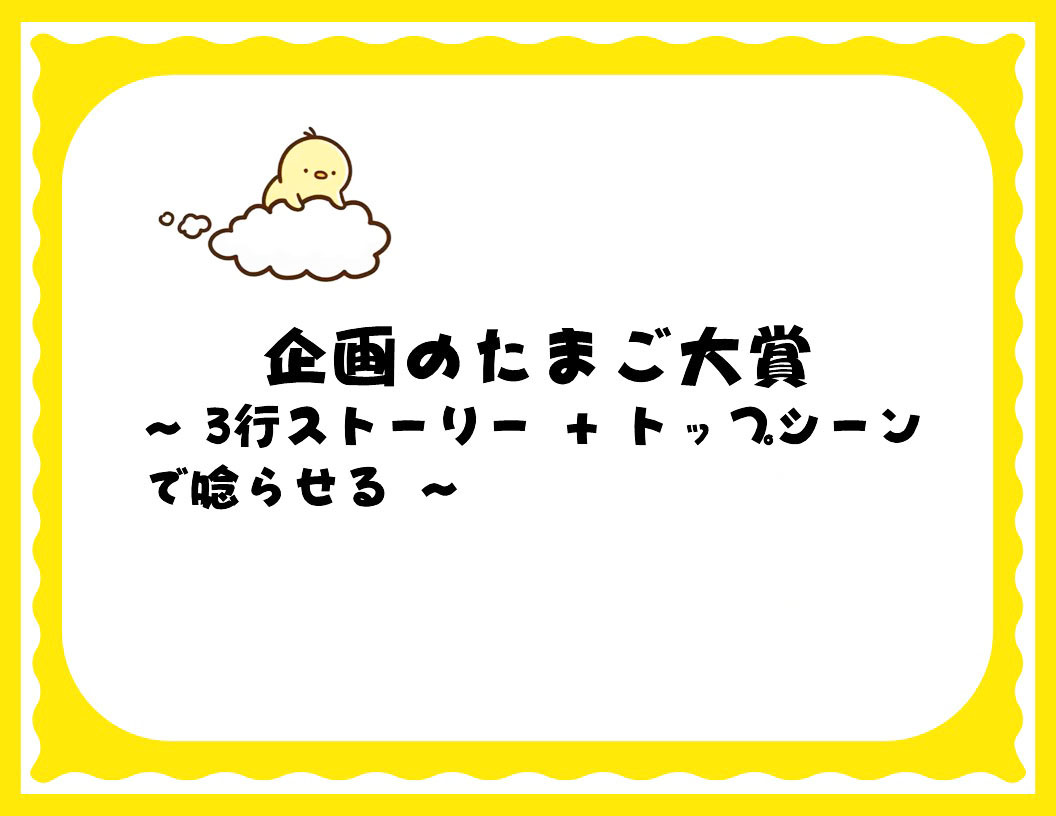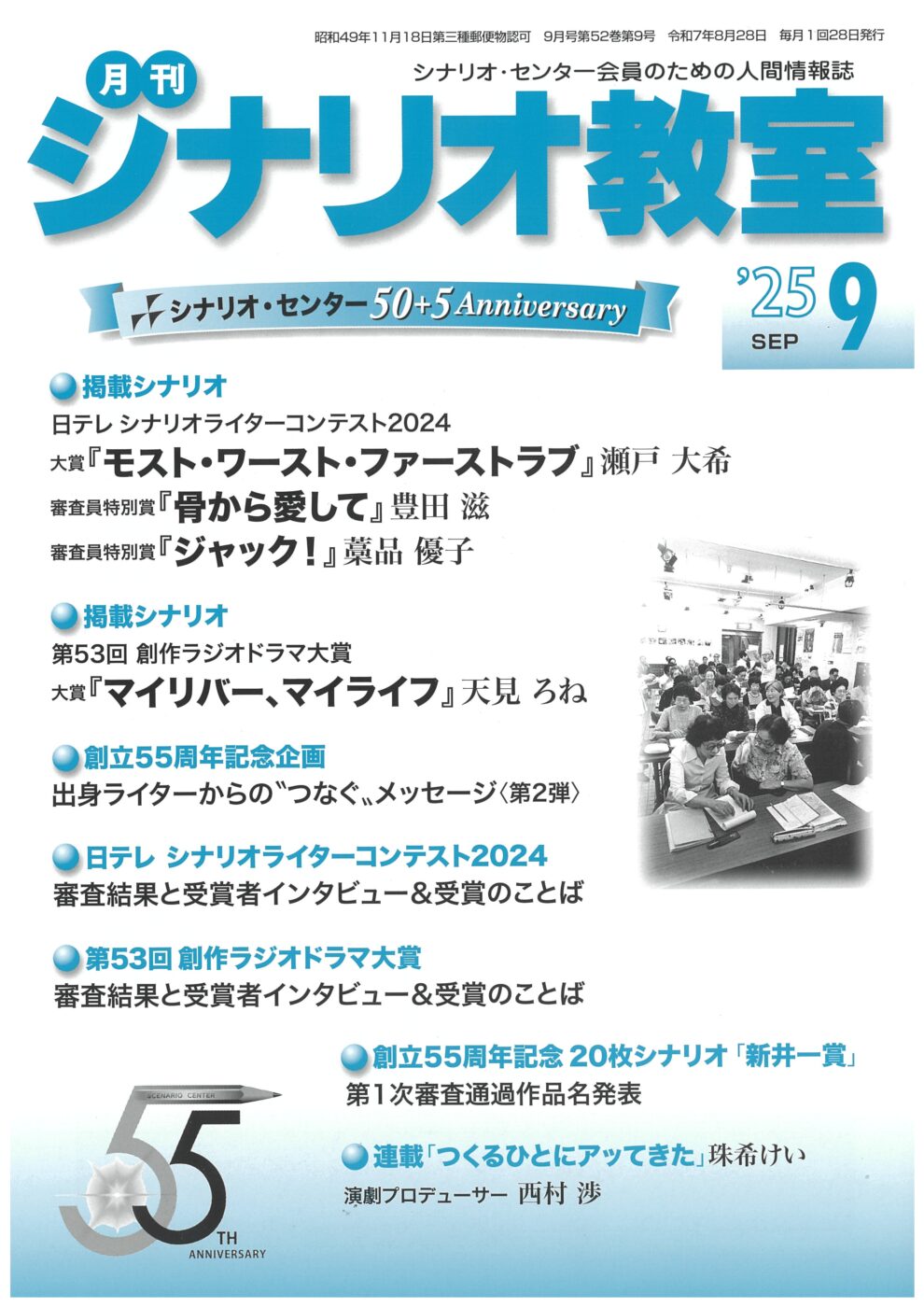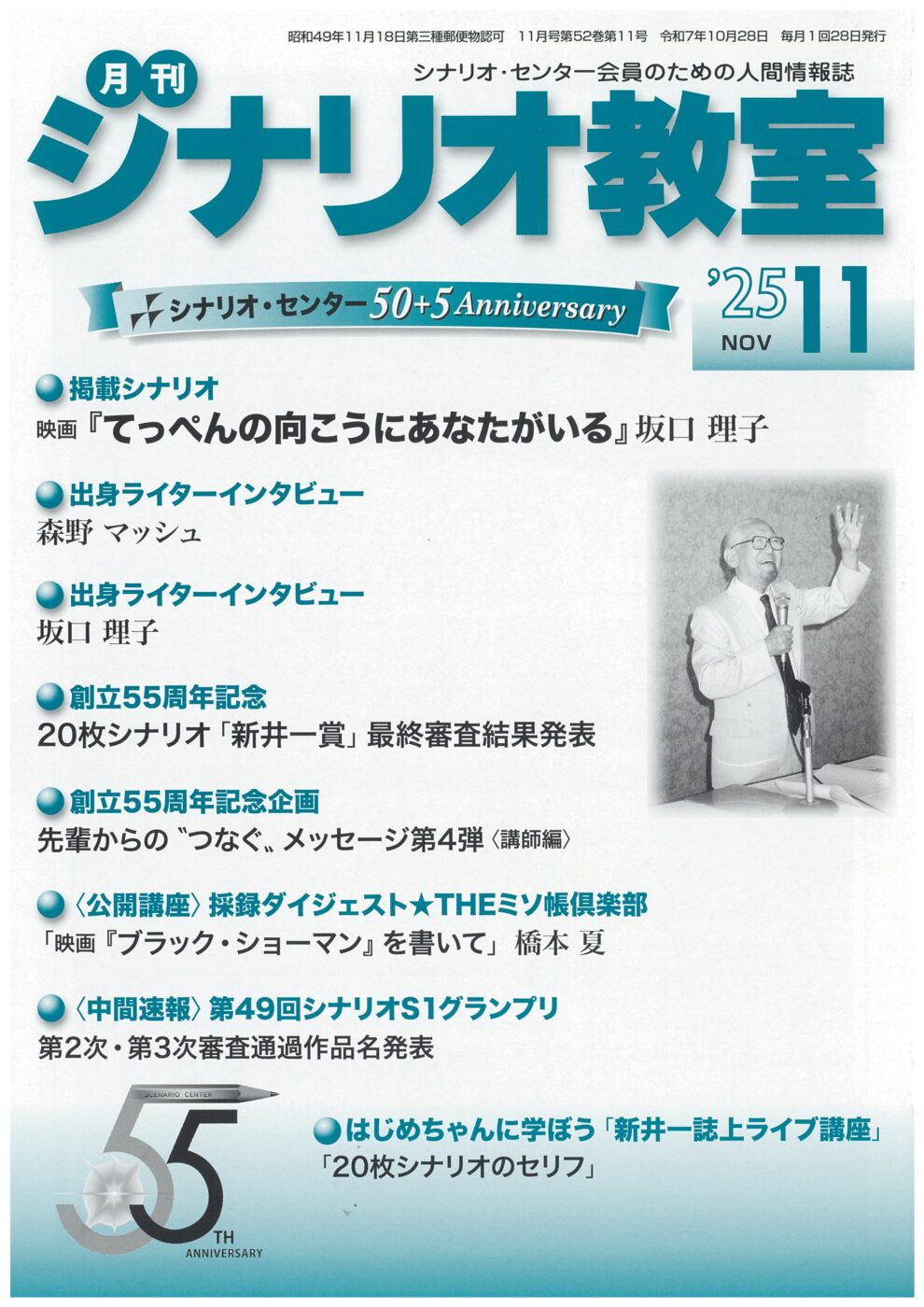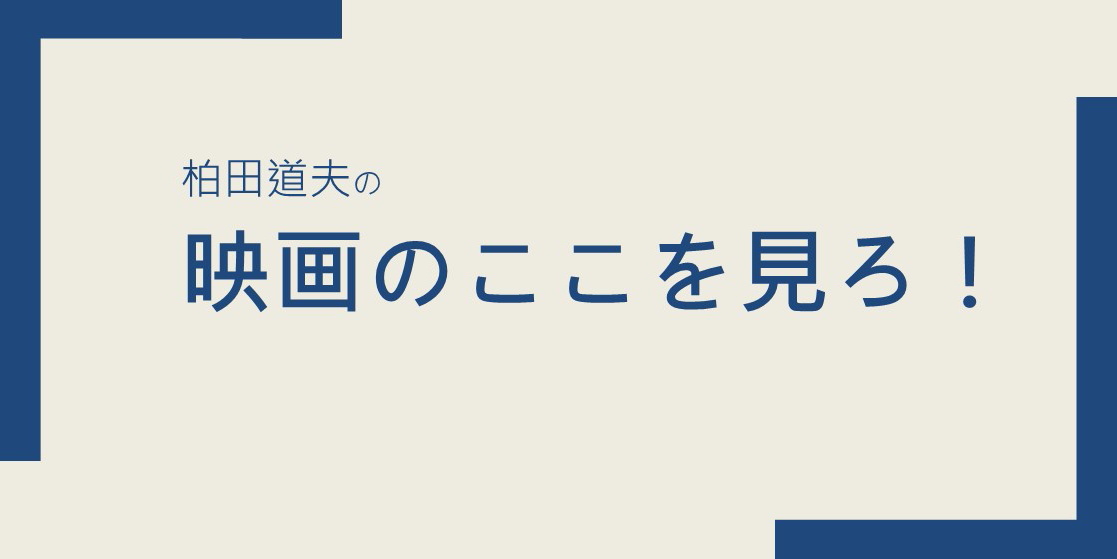シナリオ・センターではネタ帳のことをミソ帳と呼んでいます。
これには、「このアイデア、面白いな」「今すぐではないけど、いつか作品に使いたいな」と思ったことを書き留めて、“出番”がくるまで味噌のように発酵させる、という意味が込められています。
そんなミソ帳に書き込むネタが増えるように、定期的に公開講座「Theミソ帳倶楽部」を開催しているのですが、今年は創立55周年という“メモリアルイヤー”であるため、ちょっと趣向を変えて実施しております。
それが、Theミソ帳倶楽部 新シリーズ『企画のタネ』(全4回)。
物語のネタになるような“創作の種”を探している方におすすめの講座です。
こちらのブログでは、先日開催した『企画のタネ』第2弾「刑事編」の模様を一部、広報の齋藤がご紹介。刑事ものを書くときの参考にしてください。
また、「この講座に参加したことがない」という方は、「講座のタイトル通り、企画のタネになりそうなことをたくさん聴くことができるんだな」と感じていただけると思います。次回第3弾・4弾のご参加をお待ちしております!
※『企画のタネ』第1弾:カフェ経営者 編の模様はこちらから。
▼創作の“種”を見つける!
*********************************************************
なお、『企画のタネ』は「聴いて終わり」ではなく「企画ミニコンクール」も実施しています。
後日、聴講したことをもとに作品のアイデアを膨らませていただき、企画書(※専用フォーマットを使用)を提出。その中から毎回1本、ゲストが選考した『ゲスト賞』を決定。選ばれた方は「長編シナリオの個人面談」を「5,500円割引」でご利用いただけます。『企画のタネ』第2弾「刑事編」のゲスト賞が決定しましたらこちらでお知らせいたしますのでお楽しみに!
↓
== 【最新情報】「ゲスト賞」決定! ===
☆ゲスト賞
周南カンナさん『新部署発足・金は無い!』
・第2弾 刑事編のゲスト・広畑史朗さん(元警視庁刑事部参事官)による総評
設備も予算もないままスタートした警察庁の新部署「総合安全対策部」に配属された様々な登場人物たちが、色々な困難に立ち向かいながら市民を守っていく、という周南さんの企画。
斬新な設定で感心しました。
ただ、国家安全保障局は国際関係でのNational Securityを所掌しているので、外務防衛とは強く重複しますが、警察業務と大きく絡むのはむしろ内閣危機管理監の方かな……などと“重箱の隅的”な感想もなくはないのですが、とはいえ、厳密に考えなくてもシュールにドラマ展開すれば許容範囲でしょう。
シリアスでも、コメディでも、どちらのテイストであっても、色々な展開が盛り込めそうですね。
「あっ!なるほど!」と唸らされました。
*********************************************************
一片のリアリティが含まれていれば、“嘘っぽい表現”にはならない
『企画のタネ』第2弾 刑事編のゲストは、元警視庁刑事部参事官の広畑史朗さん。
当日は、本シリーズの企画・聞き手である内藤講師との対談形式で進行しました。

〇内藤講師:刑事ものを書きたい方は沢山いらっしゃると思いますし、シナリオ・センター 研修科ゼミナールの課題21本目が「刑事」なので、これから課題で書く方もいらっしゃると思うんですね。
そういうときに、やはり実際の話を聞いてから書くと作品に説得力が出るというか、「嘘っぽいな」と思われない仕上がりになるんじゃないかなと思います。
〇広畑さん:そうですね。刑事もの・病院もの・銀行ものなどのいわゆる“業界もの”は、全くの荒唐無稽だと「ちょっと……」という感じがしますけど、逆にリアリズムに走りすぎると、その業界人が観てもちょっと面白くない。一片のリアリティが含まれていれば、その他の部分が全くのフィクションであってもそれらしく見えるのではないかなと。

〇内藤講師:広畑さんは、警視庁刑事部参事官として1995年に発生したオウム真理教による化学テロ「地下鉄サリン事件」の捜査を担当された他、大阪府警刑事部長、栃木・福岡県警本部長、外事情報部長、近畿管区警察局長を歴任されました。各地のいろいろな事件に携わった、まさに“ザ・刑事さん”という経歴をお持ちです。
〇広畑さん:私は1976年に “おまわりさん”になりました。最初の数年間は“交通畑”にいて、それから「元気がいいのがいる!」ということで“刑事畑”のほうに引っ張られました。
〇兵庫県警では捜査二課長(知能犯捜査担当)でしたし、警察に採用されて一番はじめに勤務した大阪府警では南署捜査三係で、刑事の基本のキである“泥棒刑事”をやったり、各地でいろいろ事件捜査を担当しましたね。
〇内藤講師:あの、すみません……“泥棒刑事”をされていた「捜査三係」というのは「捜査三課」の中にありますよね?
〇広畑さん:はい。本部では捜査三課、所轄署刑事課では捜査三係と言います。
それではここで少し、主な「課」について説明しますね。
〇内藤講師:是非お願いします!刑事さんの「課」はネットで検索すれば出てきますけど、でもなかなかイメージが湧かないというか、覚えれらないですよね?
――この問いかけに、会場にいる生徒さんも「うんうん」と頷いています。
〇広畑さん:ではまず「捜査一課」から。一番の花形部署なので、映画やテレビドラマの“刑事もの”でもよく出てくると思います。
捜査一課で扱うのは、殺し、叩き(強盗)、傷害、放火、性犯罪などの凶悪事件。刑事の憧れは捜査一課のトップである「捜査一課長」。刑事ならみんな憧れて目指すんじゃないかな。
次に「捜査二課」。汚職、詐欺、横領、贈収賄などの知能犯罪を専門に扱う部署。選挙違反や企業犯罪も扱いますよ。
〇内藤講師:知能犯罪を扱う、と聞くとシュッとした感じの刑事さんが多いのかな、なんて思うのですが、どうでしょうか?
〇広畑さん:まあ、実際は様々なタイプの刑事の集まりではありますが、剣道が得意で背筋がいつもピンとしているような人とか、ネクタイをピシッと締めたクレバーな感じの人も中にはいましたね。
〇内藤講師:なるほど! 勿論、いろいろなタイプの刑事さんがいらっしゃるとは思いますが、刑事ものを書くとき、どんな感じの刑事さんにするか、登場人物のキャラクターを設定する際に悩んだら、こういった「課」の特徴から考えていくというのも、皆さんアリですよ。
〇広畑さん:では次に「捜査三課」。窃盗事件、泥棒や空き巣とかスリなどを扱う部署。地味ですけど、捜査三課は事件数が一番多いんです。発生数が多いので。
釣り人の生涯をフナ釣りに例えた「釣りはフナに始まり――」という格言があるそうで、「釣りの基本はフナ釣りで知り――」といった意味なのですが、これを刑事の話に置き換えるなら、捜査の基本はこの三課で知るかなと。警察署の刑事も窃盗犯担当が一番多人数ですし、刑事に登用されたときはまず盗犯担当で捜査の基本を覚えていくことが多いので、基本のキと呼ばれています。
この流れで言うと、次は「捜査四課」と思いますよね。現在は名称がいささか変わり、組織犯罪対策部(ソタイ)や暴力団対策課などに変わっています。
捜査四課では主に暴力団やヤクザが絡む事件を扱っていましたが、ソタイでは暴力団対策に加えて、覚醒剤、拳銃、国際組織犯罪、特殊詐欺(匿名・流動型犯罪<トクリュウ>)なども扱っています。
暴力担当刑事が昔は、髪型がパンチパーマだったり、強面で派手な服装もヤクザみたいだったり、どっちが暴力団員なのか分からないと言われていましたけど、今はそういう感じではないですね。そんな格好はしなくなりましたね。
〇内藤講師:そうなんですね! こうやって実際に説明していただくと、ネット記事で文字を読んで理解していくのと違って、それぞれの「課」の特徴や、そこに所属している刑事さんの雰囲気もイメージしやすいんじゃないかなと思います。
――本当に、内藤講師が言うように、こうやって直接お聞きしたほうが理解が早いのでは!
前述したお話の他、講座では「どんな人が刑事に向くのか」「捜査本部はどう設置され、どういう体制で動くのか」「捜査本部の事件名(戒名)はどう付けるのか」「印象的だった事件とは」「刑事であるが故の生活面での制約とは」「刑事の転勤について」「大切にしていた信念とは」「なぜ警察官・刑事になろうと思ったのか」「憧れの刑事はいたか」等々、いろいろなエピソードをたくさんお話しいただきました。
また、その中で、
「叩き(=強盗事件)」
「前足(=事件が起きる前の犯人の足取りや行動)」
「後足(=犯行後の犯人の行動)」
といった警察用語がいろいろ出てきました。
刑事という職業を経験された方がどういったワードを使って話すのか。これを知ることができたのも、今回この講座に参加していただいた方にとっては大きな収穫だったのでは、と思います。
リアルな話を聞くことで、登場人物のキャラクターを設定するときはステレオタイプではない発想ができるようになりますし、セリフを考えるときもその業界にいる人ならでは言葉づかいや喋り方で書くことができます。
また、冒頭で内藤講師や広畑さんが仰っていたように、その業界のリアルな部分をほんの少しフィクションに織り交ぜることで、“視聴者に違和感を感じさせない作品”として仕上げることができるのではないでしょうか。
「ネットでは検索しきれないこと」「検索できてもよく分からないこと」を具体的に把握できる場として、今後も本講座『企画のタネ』をご活用いただければ!と思っています。
『企画のタネ』シリーズ 補足情報
「知って終わり」ではなく、「じゃあこれをどういう企画にするか」という練習もできるのがこの講座の“ミソ”。
前述しました通り、毎回「企画ミニコンクール」を実施しています。
さらに、『企画のタネ』シリーズ全4回すべての応募企画の中から、優れた1本を企画書講座担当の柏田道夫 講師が選考し、『柏田賞』を決定します!『柏田賞』に選出された方には、選考コメントと「2026年開講の企画書講座」の無料受講をプレゼント。
ミソ帳に書き込むネタが増えるだけでなく、企画書を書いたことがない方にとっては企画書を書くキッカケに、普段書いている方にとっては企画書のストックを増やす機会に、なるのではないかと思います。
お得なことがいっぱいの本講座。次回第3弾・4弾からの参加でも、ゲスト賞や柏田賞を受賞するチャンスがありますので、是非ご参加ください!
「シナリオは、だれでもうまくなれます」
「基礎さえしっかりしていれば、いま書いているライターぐらいには到達することは可能です」と、新井一は言っています。“最初の一歩”として、各講座に向けた体験ワークショップもオススメです。
※シナリオ作家養成講座とシナリオ8週間講座は、オンライン受講も可能です。
詳しくは講座のページへ